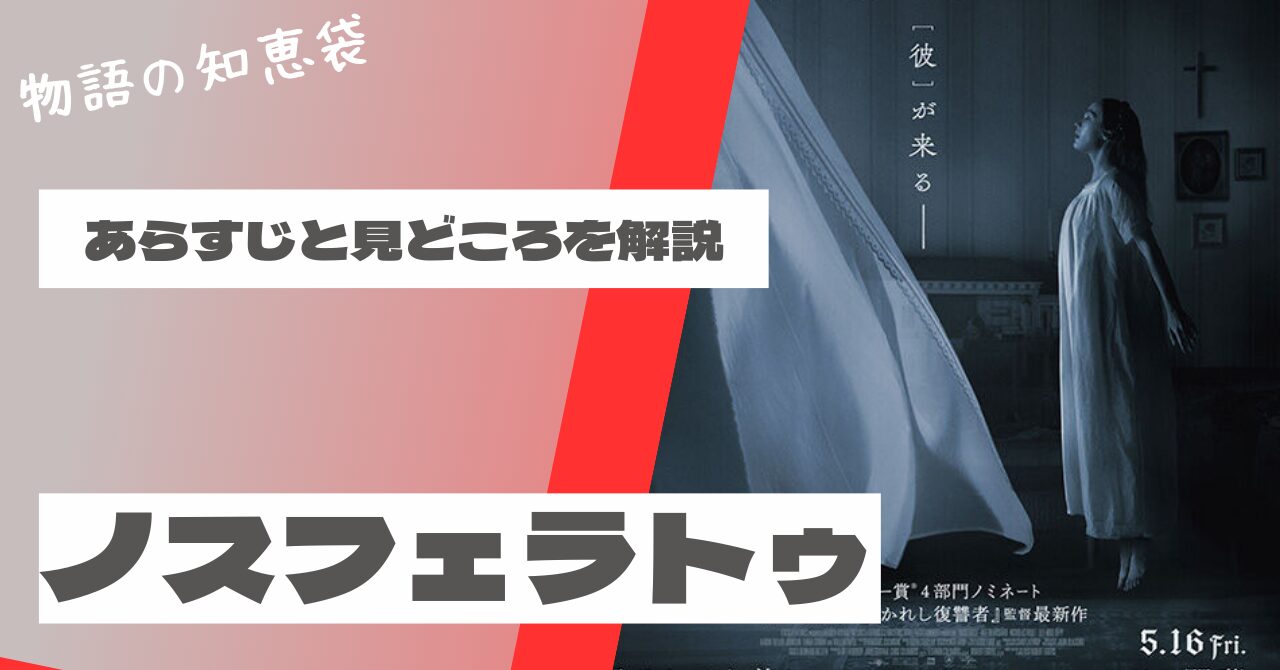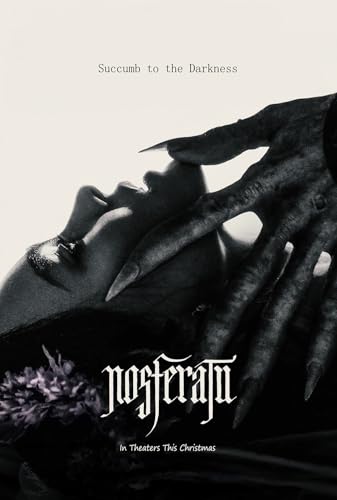
ロバート・エガース監督の映画『ノスフェラトゥ』は、ただの吸血鬼ホラーではありません。旧作との比較においても明らかなように、本作は「恐怖」を媒介にしながら、ユング心理学や宗教的象徴を巧みに織り込み、一人の女性の内面と向き合う精神の寓話として構築されています。
この記事では、あらすじを時系列順に整理しながら、物語の重要要素であるノックや不動産契約の意味、さらには“結末の象徴的構造”まで丁寧に解説します。もちろん、ネタバレを含みますのでご注意ください。
また、注目すべきトリビアや美術的背景にも触れ、従来の吸血鬼映画の枠を超えた深層的な魅力を掘り下げていきます。観る者の無意識に問いを投げかける本作の本質に迫るための、一歩深い考察記事となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
『ノスフェラトゥ』あらすじをネタバレ解説
チェックリスト
-
幼少期の祈りで吸血鬼を呼んだエレンの無意識的“契約”が物語の起点
-
不動産契約によりオルロックは“合法的”に町へ侵入し、呪いを拡大
-
ノックは狂人ではなく、儀式を媒介する“召喚者”として機能
-
クライマックスの“婚礼”はエレンの能動的な儀式として描かれる
-
吸血=性愛と死の象徴であり、ラストは快楽と解放を含む多義的結末
-
本作は恐怖の中に「女性の内的成長と精神的昇華」を描いた寓話である
映画『ノスフェラトゥ』基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | ノスフェラトゥ |
| 原題 | Nosferatu |
| 公開年 | 2024年(日本公開:2025年5月16日) |
| 制作国 | アメリカ |
| 上映時間 | 133分 |
| ジャンル | ゴシックホラー/フォークホラー/ロマンス |
| 監督 | ロバート・エガース |
| 主演 | リリー=ローズ・デップ、ニコラス・ホルト、ビル・スカルスガルド |
監督と制作背景
本作『ノスフェラトゥ』は、『ウィッチ』『ライトハウス』『ノースマン』で知られるロバート・エガース監督の4作目にあたる長編映画です。
エガースはホラーの形式を通して歴史的資料や神話、無意識の闇を可視化する作風で評価されており、本作でも1922年のサイレント映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』(F・W・ムルナウ監督)を独自に再構築しています。
幼少期から原作に心酔していたエガースが長年温めてきた企画であり、「今のハリウッドでは誰も撮らないような」手法で全編を35mmフィルム撮影。映像表現はロマン主義やバロック絵画の光と影を参照しており、現代的な再解釈と古典的な演出が融合しています。
キャストと登場人物
- エレン・フッター(リリー=ローズ・デップ):主人公。夢遊病を患う若き妻であり、物語の精神的な中心。
※ジョニー・デップの娘 - トーマス・フッター(ニコラス・ホルト):不動産業者。オルロック伯爵と契約を結び、呪いを呼び寄せる。
- オルロック伯爵(ビル・スカルスガルド):吸血鬼。性的・霊的支配者としてエレンに執着する異形の存在。
- フォン・フランツ教授(ウィレム・デフォー):吸血鬼の伝承に精通する学者。鍵を握る情報を持つ。
- ノック(サイモン・マクバーニー):トーマスの雇い主で、オルロックの協力者。
サブキャストにアーロン・テイラー=ジョンソン、エマ・コリンらが脇を固めており、全体としてゴシックな雰囲気に溶け込む巧みな配役がされています。
公開情報と評価
- 原題:Nosferatu
- 製作年:2024年
- 上映時間:133分
- ジャンル:ゴシックホラー/フォークホラー/心理ドラマ
- レーティング:PG12
- 配給:パルコ(日本)
- 劇場公開日(日本):2025年5月16日
2025年アカデミー賞では撮影・美術・衣装・メイクの4部門にノミネート。興行的にも1億ドルを超える成功を記録し、ゴシックホラーの復興を象徴する作品となっています。
ネタバレ全開であらすじを時系列順に解説

ロバート・エガース監督による『ノスフェラトゥ』は、単なる吸血鬼ホラーではなく、女性の内的変容と精神的契約の寓話です。本作は時系列に沿って整理することで、より深い意味が見えてきます。
幼少期:闇との「契約」が始まる
物語の起点は、エレンの少女時代にあります。
母を亡くし孤独のなかで育ったエレンは、祈るように「守護天使」を求めます。しかし、彼女の呼びかけに応えたのは天使ではなく、吸血鬼オルロック伯爵という闇の存在でした。
この祈りが無意識の“契約”を結び、以降エレンは夢、発作、幻覚に苦しむようになります。ここで重要なのは、彼女自身がこの呪いの発端を「意図せずに引き寄せた」という構造です。
結婚と一時の平穏
青年となったエレンは、トーマス・フッターと結婚し、ドイツのヴィスボルクで暮らし始めます。この期間、エレンの症状は収まり、いっときの平穏が訪れます。
しかし、それは“契約”が忘れられていただけにすぎません。トーマスの出張がきっかけで再び物語は大きく動き出します。
トーマスの出張と契約の罠
トーマスは雇用主ノックの指示で、トランシルヴァニアのオルロック伯爵の元へ赴きます。ノックはオルロックと密かにつながっており、トーマスとエレンを「生贄」として差し出す手はずを整えていました。
トーマスはオルロックの城で異様な体験をしながらも、内容を理解しないまま契約書にサインしてしまいます。この行為により、彼とエレンの結婚は霊的に“無効”となり、オルロックに再びエレンへ接近する力を与えてしまうのです。
呪いの拡大とオルロックの来訪
トーマスが城から脱出しようとする中、オルロックは棺に入ってヴィスボルクを目指します。その道中、疫病をもたらすネズミを引き連れ、船の乗組員たちを死に至らしめていきます。
同時にエレンの症状は再発。夢遊病、発作、幻視が頻発し、医師や周囲の人々は彼女を「ヒステリー」と見なし、拘束や投薬で対処しようとします。
ここで観客には、オルロックの侵攻が外的脅威であると同時に、彼女の内面の再覚醒でもあることがわかってきます。
エレンの覚悟と“婚礼”の準備
異端学者フォン・フランツ教授が、古文書のなかから「吸血鬼を滅ぼすには、純粋な心を持つ女性が夜明けまで引き留めなければならない」と記された一節を発見します。
エレンは自らの運命を悟り、オルロックを受け入れるという決断を下します。トーマスには真相を伏せたまま、偽の作戦(棺を燃やす)を伝え、時間を稼がせます。
クライマックス:死と快楽の“婚礼”
エレンは白いドレスをまとい、自室にオルロックを迎え入れます。このシーンは明確に「婚礼」として演出され、性愛と死が融合する象徴的儀式として描かれます。
彼女は自らの血を吸わせながら、オルロックを夜明けまで引き留めることに成功。太陽の光が差し込むと同時にオルロックは灰と化し、エレンもまた命を落とします。
最期、彼女の表情には安堵と快楽、そして解放が入り混じったような微笑が浮かんでおり、観る者の解釈に深い余韻を残します。
映画全体に流れる“時間の揺らぎ”
この作品には、明確な時系列と並行して「夢と現実」「過去と現在」の境界が曖昧になる演出が多く見られます。
エレンの幼少期の祈りと、最期の“婚礼”が円環のように結び合い、物語は「直線的な時間」ではなく「内面の循環」として進行します。
結論:一人の女性の精神譚としてのノスフェラトゥ
『ノスフェラトゥ』は、恐怖を媒介にしながら、エレンという一人の女性が「外から与えられた運命」に対し、どう能動的に対峙し、それを終わらせたかを描く物語です。
時系列を整理することで、単なる吸血鬼譚ではなく、「無意識の契約」「女性性の受容と解放」「父権的構造からの脱却」など、多層的なテーマが浮かび上がってきます。この映画は、観る人の人生観そのものを照らし返す、“魂の鏡”のような作品です。
結末の“婚礼”が意味する死と快楽

『ノスフェラトゥ』のクライマックスに描かれる“婚礼”のシーンは、吸血鬼譚における定番の「血の契約」や「死の儀式」を超えて、性愛・死・精神的昇華といった多層的な意味を内包した象徴的な場面です。ここでは、単なる自己犠牲や被害の構図ではなく、エレンという女性の能動的な選択と終焉への支配が明確に描かれています。
儀式としての“婚礼”──花嫁の装いと罠の構造
エレンは白いドレスとベールをまとい、オルロック伯爵を自室へ迎え入れます。この構図は視覚的に“結婚式”を想起させ、ふたりの関係がついに「完成」する儀式のように演出されます。オルロックは彼女の血を吸い、その瞬間に快楽に耽溺しますが、それは同時に彼の滅びへの道でもありました。
この場面の本質は「愛の契り」ではなく、死へと導く計画された罠にあります。吸血の行為は、結合ではなく断絶のための手段なのです。
快楽と死の曖昧な境界──“死の恍惚”の演出
この儀式の最中、エレンの表情は単純な苦悶や恐怖ではありません。そこには苦痛・安堵・快楽・超越が混在し、観る者の解釈を深く揺さぶります。スカルスガルド演じるオルロックが語るように、「死を迎える瞬間にこそ快楽がある」という発言は、この場面を読み解く鍵です。
このシーンは、ロバート・エガース監督も海外メディアでのインタビューで西洋美術史における「死と乙女(Death and the Maiden)」モチーフを明確に下敷きにしていると明かしており、死と官能が背中合わせであることをゴシック的美意識で象徴的に描いているのです。
エレンの能動性──支配される側から“終わらせる”側へ
物語の最初では、エレンは「闇を祈りで呼び寄せてしまった少女」として描かれており、受動的な存在に見えます。しかし最終的に、彼女は自ら“花嫁”となり、オルロックを破滅へ導く役割を選び取ります。
この“婚礼”は、女性が自らの内なる影を受け入れ、制御し、終わらせるまでの精神的旅路の終着点です。もはや彼女は犠牲者ではなく、物語を締めくくる主体者です。
多義的なラスト──解釈を観客に委ねる構造
ラストシーンは、観客によってまったく異なる意味を持ち得ます。「愛による昇華」と捉える人もいれば、「父権と呪縛からの自己解放」と読む人もいるでしょう。また、「死と官能の融合による断絶」と見る視点も可能です。
このように、『ノスフェラトゥ』は一義的な感情の押しつけを拒み、観る者の無意識を問う構造になっています。だからこそこの作品は、単なる娯楽的ホラーにとどまらず、精神の深層に触れる“寓話”として成立しているのです。
ノックの役割と物語構造における意味

『ノスフェラトゥ』において、ノックは単なる狂人や脇役ではありません。彼は、物語の根幹をつなぐ「霊的な媒介者」としての重大な役割を果たしています。その存在は、狂気と信仰、知識と儀式、偶然と必然の境界にまたがる曖昧で危険なものです。以下にその実態を詳しく解説します。
狂人ではなく“知を越えた信者”
表面的には、ノックは発狂した奇人として登場します。彼の言動や振る舞いは常人の理解を超え、不気味さを際立たせています。しかし、その背後には高度な知識と選択的信仰があります。彼はオルロックの伝承に関する古文書や禁書に精通しており、書斎には悪魔学や異端思想に関する書籍が並んでいたことが、フランツ教授の調査で明らかになります。
このことから、ノックはオルロックという存在に偶然出会ったのではなく、能動的に探し出し、崇拝するようになった人物と考えられます。彼は、理性の果てにある狂気へとたどり着いた異端の学者、あるいは「知りすぎた者」として描かれているのです。
“召喚者”としての能動的介入
ノックは、単にオルロックに従う手下ではありません。彼は、オルロックがヴィスボルクへ“侵入”するためのインフラと構造を整える「橋渡し役」として機能しています。具体的には以下のような行動が挙げられます:
- トーマスに仕事としてトランシルヴァニアを訪問させる
- 不動産取引を媒介し、オルロックに都市の居場所を与える
- 契約書にサインさせることで、社会制度上の正当性を得させる
これらは単なる狂気の行動ではなく、計画的かつ儀式的な設計です。つまりノックは“オルロック召喚の祭司”として振る舞っていたのです。
ノックが媒介した“霊的再会”
物語序盤で、エレンが子供時代に「守護天使」を求めて発した祈りによって、オルロックは彼女に“憑く”ようになります。しかし、それはあくまで霊的な接触に留まり、現実世界での接近・接触には至っていません。ここで重要なのが、ノックの介入がなければ、オルロックとエレンの物理的再会は成立しなかったという点です。
- オルロックは城から出ることを自ら望んでいなかった
- エレン一人の力では彼を現実世界に招く術がなかった
- トーマスが契約に向かわなければ、物語は始動しなかった
このように、ノックがいなければ再会は成立しない構造なのです。ノックは、エレンの“祈り”という非物質的な引力に対し、現実世界の手続きを整えた召喚者でした。
信仰者か狂人か、その境界に立つ者
このような観点から見ると、ノックは単なる狂信者ではなく、「知の果てに信仰へと踏み込んだ危険な媒介者」と位置づけられます。彼の狂気は、決して無知ゆえの妄信ではなく、理解してなお仕えるという能動的な信仰の形です。
その姿はどこか宗教的でありながら、神聖さではなく“背徳”の側に近い。まるで旧約的預言者と異端カルトの中間に位置するような、人間の知と信の臨界点を表していると言えるでしょう。
結論:ノックとは何者だったのか?
ノックは、知識によって選ばれ、信仰によって堕ちた“召喚の媒介者”である。
彼は、エレンの無意識による祈りと、オルロックの超越的存在性の間に立つ者として、物語の接続点を担いました。ノックが動かなければ、エレンの願いは夢の中で終わっていたかもしれません。したがって、彼は単なる補助役ではなく、この物語の“扉を開いた者”として、最も重要な黒幕の一人なのです。
オルロックの不動産取引が持つ“合法的侵入”の意味

なぜ吸血鬼が契約を交わすのか?という違和感
映画『ノスフェラトゥ』において、観客が最初に抱く強い違和感の一つは、オルロックが不動産契約という“人間の制度”を利用して町へ侵入するという点です。吸血鬼といえば、通常は招かれなければ家に入れない、夜に忍び込む怪異、というイメージがあります。しかし本作のオルロックは、まるで一人の市民のように契約書にサインし、法的に居住権を得て町にやってきます。
これはただの演出ではなく、「怪物が制度の裏口から入り込む」という現代的な恐怖の具現化です。
“契約”は招待状、制度は脆弱な防壁
本来、契約や法制度は人間社会を守る枠組みです。しかし『ノスフェラトゥ』では、その制度こそが怪物の侵入を可能にする抜け道になります。トーマスが無意識に署名した契約は、町そのものへの“招き”となり、オルロックに「所有者」としての地位を与えます。
ここでは伝統的な「家に招かれなければ入れない吸血鬼」という伝承が、“契約”という形式に置き換えられているのです。つまり、「招かれたから入ってきた」のではなく、「招く構造そのものが制度に内蔵されていた」という逆説が描かれます。
不動産取得が意味する“市民化”と侵略の偽装
不動産を持つということは、近代社会において「市民としての資格」「定住者としての認知」を意味します。オルロックが土地を買うという行為は、彼が都市の構成員となり、正当な手続きを経て“内側”に入るための儀式でした。
この構図は、単なるホラー演出ではなく、社会制度が逆手に取られる恐怖、すなわち“悪が擬態して合法化される”過程を示しています。怪物はもはや門を壊して入ってくるのではなく、契約という手続きを通じて静かに中へ入り込むのです。
トーマスの無知が“闇”を招いた
このプロセスにおいて重要な役割を果たすのが、不動産業者のトーマスです。彼は契約の内容を深く理解せずにサインし、自分とエレンの婚約に法的な“上書き”をされる形でオルロックを呼び込んでしまいます。契約はただのビジネス文書ではなく、霊的・社会的な境界を変質させる装置として描かれているのです。
この描写は、我々が日常的に行う契約や合意が、どれほど無自覚に“扉”を開いているかを示す寓話とも言えます。
契約とは“文明と怪異の交差点”
最終的にオルロックは、暴力的に侵略するのではなく、法を盾に堂々と町へやって来ます。これは、「人間社会のルールそのものが、怪物の侵入を許してしまう」という痛烈な皮肉です。
契約とは、正義や安全を保証するものではなく、場合によっては“闇の招待状”にもなり得る。この映画が投げかける最も深い問いの一つは、そこにあります。
オルロックの不動産契約は“静かな侵略の儀式”
『ノスフェラトゥ』における不動産契約の描写は、単なる設定ではありません。それは現代社会が抱える制度への盲信と、その制度を通じて入り込む“合法的怪異”の物語です。
怪物はドアを叩いてくるとは限らない。ときに、私たち自身が差し出したペンによって、中へ招き入れてしまうこともあるのです。この不気味な逆説こそが、『ノスフェラトゥ』が描く“契約という名のホラー”なのです。
オルロックは本当に“騙された”のか?

一見すると「罠にかかった吸血鬼」
物語のクライマックスでは、エレンが自らオルロックを寝室に招き入れ、夜明けまで血を吸わせ続けるという展開が描かれます。結果、朝日を浴びたオルロックは崩れ落ち、塵となって滅びてしまいます。
この構図だけを見ると、「エレンが自らを囮にしてオルロックを欺き、日の光で倒すことに成功した」というふうに見えるかもしれません。1922年のオリジナル版『吸血鬼ノスフェラトゥ』にも通じる、わかりやすい因果応報的な終幕です。
しかし、2024年のロバート・エガース版はそこに“解釈の余地”を強く残しています。
死と快楽は同居していたのか?
俳優ビル・スカルスガルド(オルロック役)はインタビューで、終盤のシーンについて「死とエクスタシーが交差する瞬間」と表現しています。この発言は、オルロックの死が単なる敗北ではなく、“恍惚と救済”を含んだ破滅であった可能性を示唆しています。
彼が最後にエレンの腕の中で死を迎える様は、あたかも永遠の渇望が満たされ、長き不死の苦しみに終止符が打たれる「美しい終わり」にも見えるのです。
なぜオルロックは死を受け入れたのか?
このラストを“罠”としてだけ見ると、オルロックは単に愚かだったように感じられるかもしれません。しかし、彼は決して単なる被害者ではなく、ある種の意志をもって滅びを受け入れた存在と読むことも可能です。
考えられる理由は以下の通りです。
永遠への倦怠と純粋な魂への渇望
何世紀にもわたって孤独と飢えに苦しみ続けたオルロックは、エレンのような“純粋な魂”との接触こそが自らの存在に意味と終焉をもたらすと理解していた可能性があります。彼にとって、エレンは単なる“餌”ではなく“終末の伴侶”だったのです。
エレンへの執着と判断の停止
「花嫁」としてのエレンに取り憑かれていたオルロックは、彼女と結ばれることのみに集中し、日の出という最大の弱点への警戒を忘れていたとも解釈できます。彼女との結合が“破滅”であることすらも、彼にとっては無意味だったのかもしれません。
知っていて抗わなかったという可能性
理性的かつ知的な存在であるオルロックが、まったく気づかずに朝を迎えたとは考えにくいでしょう。むしろ自らの滅びを受け入れた上で、最後の一滴までエレンにすがったという可能性こそ、本作の多義性を象徴しています。
騙されたのか、満足して滅んだのか?
この問いに対する答えは、“両方”である可能性が高いというのが、本作における最大のポイントです。
- 表層的には、オルロックはエレンの罠にかかり滅びたように見えます。
- しかし深層的には、「彼女に抱かれて死ぬ」という行為そのものが、望まれた終焉であり、快楽と解放を伴った選択だったとも解釈できます。
解釈が観客に委ねられている理由
このように、ロバート・エガース版『ノスフェラトゥ』は、明確な善悪や勝敗に回収されない寓話構造をとっています。その多義的な結末こそが、観客それぞれの人生観や無意識に問いを投げかける仕掛けになっており、ただのホラー映画では終わらない深い余韻と思索を生む大きな理由なのです。
ノスフェラトゥを深く読み解く解説とネタバレ考察
チェックリスト
-
2024年版はエレンが語り手となることで、旧作とは視点・主題が大きく異なる
-
恐怖の本質が「外部の脅威」から「内なる無意識」へと移行している
-
ユング心理学を応用し、吸血鬼は“内面の影”や“自己の分身”として描かれる
-
吸血=性愛・死・精神統合の象徴であり、“婚礼”は能動的儀式として演出される
-
本作は宗教的救済のモチーフを内面の贖罪と昇華へと再構築している
-
女性の精神疾患や抑圧の歴史的批判も織り込み、社会的テーマを重層的に扱っている
旧作との違いは“誰が主語か”にある

『ノスフェラトゥ』(2024年版)は、1922年のムルナウ版、1979年のヘルツォーク版といった旧作と比べて、“誰が物語を語るのか”=主語の変化によって、作品全体の視点・主題・感情の構造が根底から刷新されています。
特に「エレンが語り手であり、主体者である」ことが最大の特徴であり、これが映画の深層的な意味を大きく変えています。
1922年版:吸血鬼=外から来る災厄
ムルナウ監督によるオリジナル版では、主人公は男性のトーマス・ハーカーです。彼の視点で物語が進行し、オルロック伯爵は“ペストの象徴”として都市に災厄をもたらす外的存在として描かれました。
エレンは最終的に吸血鬼を倒すために自己犠牲を払いますが、その内面はほとんど描かれず、物語上の装置として機能しているにすぎません。
主語は終始「男性」であり、女性は語られ“る”存在です。
1979年版:哀しき怪物と受け身の女性
ヘルツォーク版では、オルロックに哀しさと孤独が加味され、人間性を帯びた“悲劇的怪物”として再解釈されました。エレン(ルーシー)は少し能動的に描かれますが、それでも物語の重心はトーマスにあり、吸血鬼との対峙も彼を中心に展開されます。
ここでもエレンは「犠牲者」であり、男性の物語の中に添えられた存在に留まっています。
2024年版:語り手としてのエレン
ロバート・エガース監督による最新作では、視点は完全にエレンに置かれています。
彼女は“語られる”存在ではなく、物語の中心を成す“語る主体”として描かれます。
幼少期の祈りによってオルロックという闇を呼び寄せた彼女は、長年その影に囚われながらも、最終的には自ら彼を迎え入れ、朝日で消滅させるという決断を下します。この一連の選択は、従来のような「救われる女」ではなく、「自ら運命を終わらせる主体者」としての女性像を強調しています。
主語の変化が意味するテーマの変化
視点が変われば、語られる主題も変わります。
以下は各時代ごとの主題の違いです:
- 1922年版:社会不安・疫病・外部からの脅威
- 1979年版:孤独と呪い・他者とのすれ違い
- 2024年版:内面の闇・無意識・女性の主体性
今作における恐怖の根源は、外部ではなく「自分の中にあるもの」です。オルロックは、エレンの祈りに応じて現れた“守護のはずの存在”であり、彼女の影や欲望、抑圧といった精神的要素が具体化した存在でもあります。
「語り手の性」が物語を変える
ここで重要なのは、主語=語り手が変わることで、吸血鬼譚というジャンルそのものの枠組みが再構築されたという点です。
旧作では、吸血鬼とは「侵略者」であり、「被害者」を襲うという構造が固定されていました。しかし、2024年版では、吸血鬼とは「かつて自らが呼び寄せ、内に住まわせた存在」であり、それをどう扱うかが物語の核心になります。
エレンの物語は、恐怖に支配される女性の話ではなく、恐怖を“飼いならし、見送り、昇華させる”女性の物語です。
終幕が象徴する視点の完成
“婚礼”の儀式においても、エレンは白いドレスを着てオルロックを迎え入れますが、それは単なる犠牲ではありません。
彼女はトーマスにも教授にも頼らず、自らの内なる闇に主導的に向き合い、結末を演出する役割を担うのです。
このとき、彼女は「語られたヒロイン」ではなく、「物語を終わらせる語り手」としての姿を完成させます。
『ノスフェラトゥ』(2024年)は、誰が主語なのかという一点において、過去作とはまったく異なる物語構造を提示しました。
それはホラー映画という枠を超え、自己認識と内面の解放、性と死の対話という深層テーマへと物語を導く選択でもあります。
“誰が語るのか”が変われば、“物語の意味”も変わる——この視点の転換こそが、2024年版が最も革新的である理由なのです。
ユング心理学で読み解く影と欲望

『ノスフェラトゥ』は、単なるホラー映画ではなく、人間の深層心理を映し出す精神的寓話として構築されています。その核心にあるのが「影(シャドウ)」「アニマ(内なる異性像)」「集合的無意識」といったユング心理学の概念です。これらを手がかりに読み解くことで、登場人物や物語の象徴に隠された“もう一つの真実”が見えてきます。
なぜユング心理学で読み解く必要があるのか?
この映画では、表層的な「吸血鬼との闘い」だけでなく、主人公エレンの内面の葛藤と変容のプロセスが物語の主軸になっています。夢、幻覚、発作といったモチーフが繰り返される演出は、まさに無意識の領域に沈んだ感情や欲望が浮上するプロセスを可視化しているのです。
つまり、本作を理解するうえで欠かせないのは、外部の脅威としての吸血鬼ではなく、エレン自身の内なる影との対峙という構造です。その解釈の鍵を握るのが、ユングの深層心理学です。
シャドウ:オルロックは“自分の中の闇”
ユングが提唱した「シャドウ(影)」とは、個人が意識の中で拒否し、無意識へと押し込めた自己の側面のことです。
作中でエレンは、幼少期の“祈り”によってオルロックを呼び寄せてしまいます。これは単なる宗教的儀式ではなく、自分の中にある「依存」「欲望」「支配されたい願望」などの影を引き寄せた行為として読み解くことができます。
オルロックは“他者”ではなく、彼女が向き合うべき内なるシャドウの化身であり、その影と向き合わずに外に追いやったとき、彼は災厄として現実を侵食していきます。
アニマ:女性性の覚醒と自己統合
ユングにおける「アニマ」とは、男性の中にある女性的側面を指しますが、本作では逆に、エレンが「オルロック=男性的破壊衝動」と結びつくことで、自己の中にある“異性性”を統合しようとするプロセスが描かれます。
吸血という行為は、単なる性的メタファーではなく、「自他の境界を越え、自己の一部を受け入れる儀式」としての象徴的意味を持ちます。エレンが最終的にオルロックを“内面の一部”として受け入れ、終わらせる構図は、アニマとの融合=精神の統合と捉えることができます。
集合的無意識:神話的パターンとしての“吸血鬼譚”
ユングの理論では、「集合的無意識」とは、人類に共通する象徴や神話的パターンが蓄積された領域です。吸血鬼という存在そのものが、古代から繰り返されてきた“死と再生”“誘惑と滅び”の元型的象徴といえます。
オルロック伯爵の姿は、「病」「異物」「性的支配者」「死神」など、多重の元型を集約しています。これを女性が“花嫁”として迎え入れ、自ら終焉へ導くという構図は、ユング心理学で語られる「影との統合」や「魂の夜の通過」というテーマと深く響き合います。
精神の寓話としての『ノスフェラトゥ』
このように、本作における吸血鬼との対決は、表層的な「善悪の戦い」ではなく、“自己の無意識をいかに受け入れ、統合するか”という魂の旅として描かれています。ユングの視点を通すことで、映画の細部に散りばめられた象徴が一つの大きなテーマに収束していく様子が明瞭になります。
恐怖とは、自分の内にある“見たくないもの”を映し出す鏡であり、それを迎え入れることでしか、人は自由になれない――そうしたメッセージが、この映画の深層には込められているのです。
宗教的象徴が語る罪と救済の構図

『ノスフェラトゥ』は、吸血鬼という恐怖の存在を借りながら、キリスト教的モチーフや信仰の構造を再解釈し、罪と救済を巡る精神的寓話を築き上げています。ここでは「祈り」「婚礼」「贖罪」「殉教」といった宗教的要素が複層的に織り込まれ、エレンというひとりの女性を通じて、“信仰と超越”の意味が深く掘り下げられています。
祈りが引き寄せたのは“守護”ではなく“闇”
物語の発端で、幼いエレンは孤独から救われることを願い、「守護天使」へ純粋な祈りを捧げます。通常、祈りは神聖な導きを求める行為ですが、この映画では祈りが異形の存在=吸血鬼オルロックを招くという逆説的な展開を取ります。
これは、祈りの背後にある無意識の欲望や、純粋さの中にひそむ“影”が具現化したものであり、「信仰の光」がそのまま「闇の扉」となる可能性を示しています。
“婚礼”という擬似宗教儀式に潜む死と昇華
クライマックスでエレンが白いドレスをまとい、吸血鬼オルロックを自室に迎え入れる場面は、キリスト教的な“婚礼”の象徴性を強く帯びています。本来、婚礼とは祝福と繁栄、神と人間の契約を象徴する神聖な儀式ですが、ここではそれが死と破滅を導く儀式として描かれるのです。
血を交わすこと=“結合”は、性愛と信仰が交錯する儀式的行為であり、エレンが自ら差し出すことで起きるのは救済ではなく、意志による破壊=昇華です。この“婚礼”はただの服従ではなく、支配を裏返しにした策略であり、聖と俗の境界線が溶け合う瞬間です。
エレンの行為は殉教か、それとも主体的な贖罪か
過去作のエレン(あるいはルーシー)は、吸血鬼を倒す“受動的な犠牲者”として描かれていました。しかし本作では、エレンは自らの過去――祈りによって招いた存在と真正面から向き合い、能動的に破滅の場を演出する“聖なる意志”の持ち主になります。
これは殉教者ではなく、罪と向き合い、それを自分の手で終わらせる者としての贖罪者です。祈りだけではなく、“行為”によって結末を制御する姿に、現代的な信仰の再定義が読み取れます。
聖と俗、肉体と霊魂の融合が導く“救済の曖昧さ”
エレンの死は単なる終焉ではありません。彼女の最期の表情には、痛みと快楽、解放と充足が同時に浮かんでいます。これはキリスト教美術にしばしば描かれる「恍惚の聖女」のイメージにも通じ、死=苦しみであると同時に、魂の解脱であることを示唆します。
この曖昧さは、「罪を背負ったまま終わらせること」もまた救済たりうるという、キリスト教的構造を反転させた内面的神学を体現していると言えるでしょう。
信仰と救いを“外”から“内”へ転換する物語構造
本作において十字架や教会といった明示的な宗教的モチーフは控えめです。しかし、物語全体が構造的に以下のようなキリスト教的な流れを内包しています:
- 原罪の発端:幼いエレンの無垢な祈り
- 堕落と苦悩:オルロックの侵入と支配
- 悔悛と理解:自身が闇を招いたことへの気づき
- 贖罪の行為:自ら命を賭けて終わらせる決断
- 救済(昇華):死によって支配を終わらせ、魂の自由を得る
この一連の流れは、伝統的な宗教の物語構造を踏襲しながら、あくまでも個人の内面の物語へと変換されている点が重要です。
まとめ:精神の宗教劇としてのノスフェラトゥ
『ノスフェラトゥ』は、恐怖を描きながらも、本質的には「誰が祈り、誰が救うのか」という問いに向き合う作品です。エレンという女性は、信仰に身を委ねるのではなく、自らの意志で闇を終わらせることで、新たな“救済の形式”を体現する存在として描かれています。
この映画が示す宗教的象徴とは、固定化された信仰ではなく、内的闇を引き受け、昇華へと向かうプロセスそのものです。それは外から与えられる神の救いではなく、自らが選び取る「精神の超越」であり、現代における“信仰の可能性”そのものを描いているのです。
精神疾患と19世紀女性の描写問題

『ノスフェラトゥ』は、ただのホラー作品ではありません。本作は、19世紀の女性に対して社会が与えていた「精神疾患」というレッテルを通して、ヒステリーや夢遊病、そして性の抑圧という歴史的背景を批評的に描いています。主人公エレンの苦しみは、“病”ではなく、時代に規定された「女性」と、それに伴う構造的な抑圧そのものを象徴しています。
医学が作った「女性の病」としてのヒステリー
19世紀ヨーロッパでは、女性が抱える感情的・性的な苦しみは、しばしば「ヒステリー」という曖昧な精神疾患として診断されました。
当時の医療では、女性の身体と精神が“過敏”で“理性的でない”と見なされており、泣く・叫ぶ・興奮する・性欲を示す――こうした行為は病的とされました。
このヒステリーという概念は、女性の自己表現を制限し、医療と父権的価値観が結託して支配を強化する装置でもありました。
エレンが体現する夢遊病と社会的無理解
劇中、エレンはたびたび幻覚や発作に襲われ、意識が混濁した状態で夢のような空間をさまよいます。この症状は、当時「夢遊病(ソムナンビュリズム)」とも呼ばれ、無意識の行動とされていました。
重要なのは、彼女の症状が医師や社会から“異常”とされ、薬漬けや拘束といった処置がなされる点です。これは当時の女性がどれほど身体的自由や発言の権利を奪われていたかを如実に示しています。
性と欲望をめぐる抑圧の構造
『ノスフェラトゥ』では、吸血そのものが性的な象徴として扱われます。エレンの血を吸う行為は、支配・快楽・罪・破滅をすべて内包しており、それに抗う彼女の姿勢は、抑圧された女性が“自らの性”を取り戻す過程として読めます。
また、彼女が幼少期に祈った“守護”が吸血鬼を呼び寄せるという構造も、無垢であろうとする純潔観がいかにして呪いを内面化させてきたかを暗示しています。
能動的な選択による抑圧からの離脱
エレンは最終的に“婚礼”という儀式の形で吸血鬼を迎え入れ、夜明けまで引き留めて葬るという選択をします。
この行為は、自己犠牲でありながらも自分の意志によって「支配する者を終わらせる」という能動性を帯びています。
つまり彼女は、医学や宗教、社会的規範が押しつけてきた「女性とはこうあるべき」という型を、死と引き換えに打ち破った存在でもあるのです。
まとめ:精神疾患という“言い訳”の暴力
『ノスフェラトゥ』は、19世紀の“女性=病”という概念を根底から疑い、精神疾患の診断がいかにして社会的な抑圧の正当化に使われてきたかを暴きます。
それは今を生きる私たちにとっても、ジェンダー、精神医療、自由意志の本質を見つめ直す契機となるものです。
この作品におけるエレンの姿は、単なるヒロインではありません。「狂気」とされた女性の中にある理性と意志を、スクリーン上に浮かび上がらせた精神的な闘士なのです。
ロバート・エガース監督の作家性分析

歴史と神話の境界を曖昧にする演出
ロバート・エガース監督の作品に共通するのは、「歴史的事実」と「超自然的伝承」の緊張関係を、極めてリアルに再現しながらも、あえてその境界をぼかす手法です。
たとえば『ウィッチ』(2015年)では、17世紀ニューイングランドの禁欲的な信仰生活の中で魔女の存在を現実と錯覚させ、『ライトハウス』(2019年)では孤立した灯台守たちの精神崩壊を、神話的怪異と密接に結びつけて描きました。
『ノスフェラトゥ』もその系譜にあります。1838年のドイツという厳格なキリスト教社会を舞台にしながら、闇の中に潜む“異形”=吸血鬼を、現実を侵食する「心の闇」として描いています。これは彼の持ち味である「歴史の正確さ」と「神話の曖昧さ」の両立によって成り立っています。
フォークホラーに通底する「土着の恐怖」
エガースは“フォークホラー”の再定義者とも言える存在です。
彼の恐怖演出は、ジャンプスケアに頼ることなく、「風習」や「信仰」がいかに人を狂わせるかに焦点を当てています。『ノスフェラトゥ』でも、吸血鬼オルロックの恐怖は決して突発的な襲撃ではなく、少女時代に交わした「祈り」という“信仰の暴走”から始まります。
つまり、エガース作品における恐怖とは、外から来る怪物ではなく、内側から生まれる異常なのです。この構造こそが、彼のフォークホラー的手法の核にあります。
厳密な時代考証と撮影様式の徹底
ロバート・エガースの映画は、異常なまでのリアリズムと物理的没入感に裏打ちされています。『ノスフェラトゥ』では全編を35mmフィルムで撮影し、キャンドルの光だけでシーンを撮るなど、徹底したこだわりを貫いています。
セットも約60以上を建設、2000匹のネズミを実際に用いるなど、現代のCG主流の映画とは一線を画する物理的リアリズムを追求しています。これにより、鑑賞者は物語の中に“迷い込む”ような体験をすることになります。
観客の「知覚の揺らぎ」を誘発する
エガースは、登場人物だけでなく観客にも「これは現実か、幻想か?」という不安定な知覚を与え続けます。
『ライトハウス』での幻覚と現実の曖昧な境界線は顕著でしたが、『ノスフェラトゥ』ではさらに進化し、登場人物の夢と現実が二重構造で進行する演出を多用しています。
これは、映像の陰影、音響の残響、演者の身体表現(とくにリリー=ローズ・デップによる発作シーン)によって強調され、まるで夢の中で夢を見るような感覚を引き起こします。
「恐怖」を“予兆”として描く美学
最も特筆すべきは、エガースの恐怖演出は直接的な怖さよりも“気配”や“予兆”を重視している点です。
『ノスフェラトゥ』では、オルロックの登場すらも、最初は影や夢、奇妙な偶然の連鎖として現れます。彼の作品には常に、「来るぞ……」という不穏な空気が漂っており、その“待つ時間”こそが最大の恐怖になります。
このように、ロバート・エガースは恐怖を演出ではなく“空気そのもの”として成立させる稀有な監督であり、その作家性は『ノスフェラトゥ』においても明確に結実しています。
本作品のトリビアを紹介
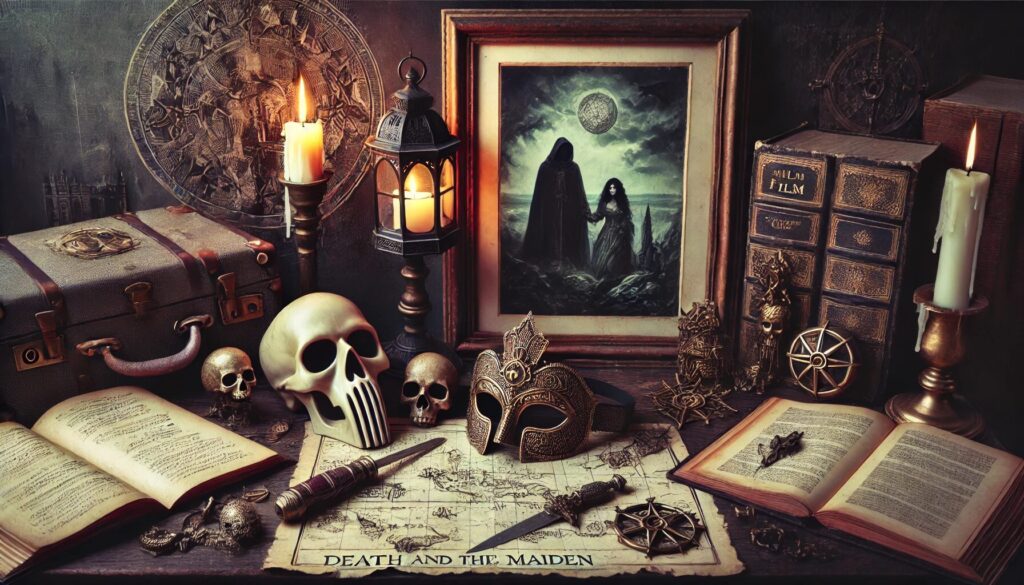
『ノスフェラトゥ』は、単なるリメイクやホラー映画の枠を超え、映画史・芸術史・精神分析など多層的なモチーフを内包しています。ここでは作品をより深く楽しむための、興味深いトリビアをいくつか紹介します。
原作クレジットはやはり“存在しない”?
本作はブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』に強く影響を受けた1922年の『ノスフェラトゥ』のリメイクですが、今回もあえて「原作:ドラキュラ」とは明記していません。これは、著作権問題に揺れたオリジナル版へのオマージュとも解釈されており、「ノスフェラトゥ」という名称そのものが、ストーカー家との訴訟を避けるために生まれたものでした。
撮影には実際の古城が使用された
エガース監督はロケーションに強いこだわりを持つことで知られており、本作でも実在する東欧の城や村が撮影地に使われています。とくにオルロックの城として登場する建物は19世紀建築をそのまま利用し、デジタル処理では再現できない「質感の重み」を生んでいます。
35mmフィルム撮影による“古典的な質感”
現代の映画の多くがデジタルで撮影される中、本作は35mmフィルムで撮影されました。これは監督のロバート・エガースが「1920年代の映画が持つ視覚的質感」にこだわったためで、画面には微細なノイズや光の揺らぎが映し出されます。このアナログ感こそが、“夢と悪夢の境界”を曖昧にする演出に直結しています。
「死と乙女」モチーフの美術的引用
クライマックスでの“婚礼”シーンは、美術史における「死と乙女(Death and the Maiden)」というモチーフの映像化です。これは中世ヨーロッパの絵画や詩にしばしば登場するもので、若い女性と骸骨や死神が抱擁する構図を通して、死と性愛の曖昧な関係を描くものです。
映画ではエレンが白いドレスを纏い、死を象徴するオルロックに抱かれる姿がまさにこの構図を踏襲しており、美術的教養を前提とした演出になっています。
オルロック役には複数の表現技法が重ねられている
オルロック伯爵は、メイクだけでなく演出・ライティング・アングルによって一貫した“不在のような存在感”が付与されています。特に光源が当たらない位置でぼんやり立つシーン、影だけが移動する演出は、1922年版の影法師の演出を引用したうえで、より幽霊的な存在として再構築されています。
「エレン」の名前が変更されなかった理由
他の登場人物名(例:ハーカー → トーマス)などは現代的に調整されているにもかかわらず、エレンという名だけは1922年版と同一のまま使用されています。これは「物語の中核を女性に置く」という現代的意図に加え、原作と歴史的連続性を担保する象徴的な選択とも受け取れます。
セリフの少なさは“沈黙の演技”への挑戦
本作ではセリフの量が極端に抑えられており、登場人物の感情表現の多くが“視線・呼吸・間”に委ねられています。これは無声映画的演出の継承でもあり、1922年版『ノスフェラトゥ』へのオマージュと位置付けることができます。
結末の光の使い方に“ルネサンス宗教画”の影響
オルロックが滅びるシーンの光の演出は、実は多くのルネサンス時代の受胎告知や磔刑図に使われる光の射し方(ディヴァイン・ライト)を参考にしています。この“神の光”のような表現が、死の瞬間を“救済”としても読み取れるように仕組まれているのです。
エンドロールの構成にも意味がある
本作のエンドロールでは、通常のクレジットの順番とは異なる構成が取られており、主演のリリー=ローズ・デップの名前が単独で際立つように編集されています。これは、この物語が「彼女の物語」であることを最後まで印象付ける演出です。
このように『ノスフェラトゥ』は、細部にまで意味と演出意図が込められた作品です。背景知識を踏まえることで、より深く本作の世界観とテーマを堪能することができるでしょう。
ノスフェラトゥのネタバレ解説まとめ:物語と象徴の核心を整理
- 幼いエレンの祈りが吸血鬼との霊的契約の起点となる
- エレンは守護天使を求めたが闇の存在オルロックが応えた
- トーマスの契約が夫婦関係の霊的効力を無効化する構造
- オルロックの来訪はエレンの内的覚醒とリンクしている
- フォン・フランツの古文書が「女性による吸血鬼の滅殺条件」を示す
- エレンは“婚礼”の儀式を通してオルロックを破滅へ導く
- 吸血と快楽の融合が“死と乙女”のモチーフを視覚化する
- ノックは狂人ではなくオルロック召喚を担う信仰的媒介者
- 不動産契約は吸血鬼の合法的侵入を成立させる社会的装置
- オルロックは死を受け入れた“滅びを望む怪物”として描かれる
- 本作は1922年版とは異なり“エレン視点”で語られる物語構造
- ユング心理学の「シャドウ」概念が吸血鬼の象徴性と一致する
- 宗教的儀式が救済でなく自力で終焉を選ぶ構造へと変換されている
- エレンの発作は19世紀的な“女性への精神疾患ラベリング”の批判を含む
- 映像演出にはロマン主義絵画やルネサンスの宗教画的構図が活用されている