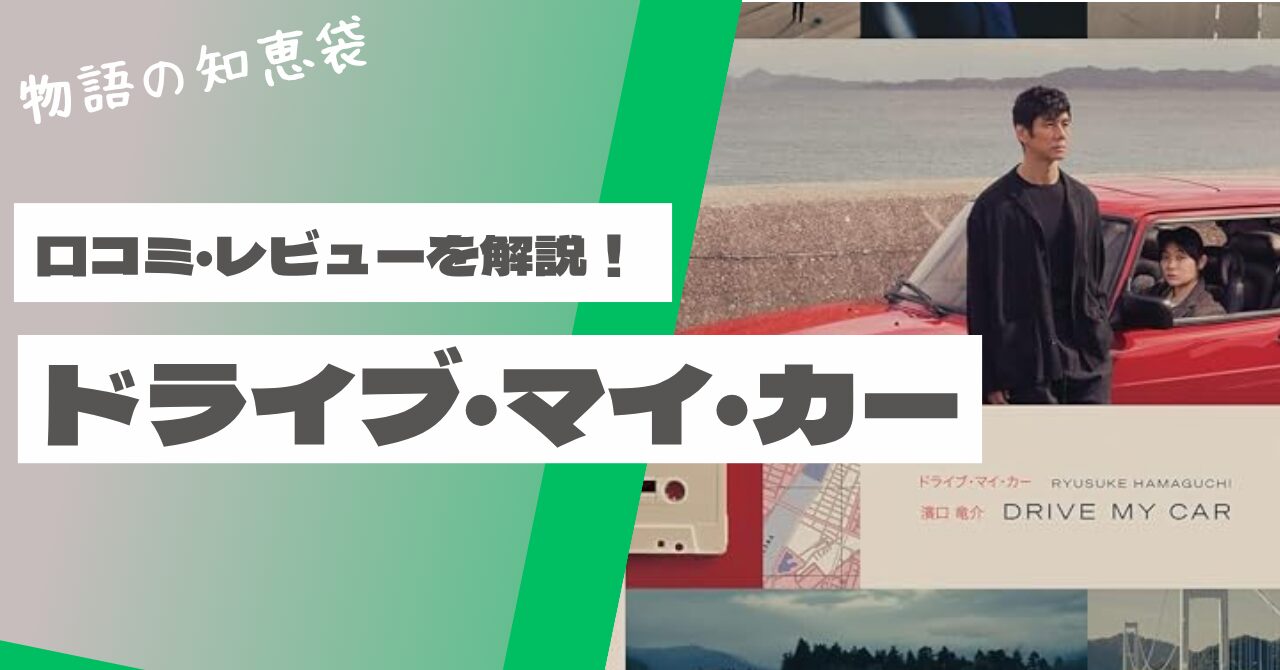映画『ドライブ・マイ・カー』を観たあと、「良さが分からない」「正直つまらない」と感じた方は少なくありません。淡々とした会話、棒読み演技のように聞こえるセリフ、そして感情が動かない登場人物たちのやりとりに、違和感や退屈さを覚えた方もいるでしょう。特に、静かな車内で交わされるセリフの応酬や、唐突にも感じられる韓国ラストに戸惑ったという声も見られます。
「気持ち悪い」とまで言われるこの作品の正体とは何なのでしょうか。わかりにくさをあえて演出する意図や、「つまらない」の先にある意味を丁寧に読み解くことで、見えなかった魅力に気づけるかもしれません。本記事では、そんな疑問や違和感を一つずつひも解きながら、映画『ドライブ・マイ・カー』が投げかけるメッセージに迫ります。
本作品のラストの意味など詳細な解説を知りたい方はこちらの記事もご覧ください!
ドライブ・マイ・カー|ネタバレ解説とラストの意味を考察
ドライブマイカーが気持ち悪いと感じる本当の理由とは
チェックリスト
-
映画の「わかりにくさ」が共感を妨げ、「良さが分からない」と感じさせる
-
登場人物の感情が表出せず、沈黙や余白が多い構成が距離感を生む
-
「気持ち悪い」と感じるのは説明のなさや不穏な空気が原因
-
棒読み演技は監督の意図による演出手法であり“感情の余白”を作っている
-
「つまらない」と感じる時間こそが、観客の内面に静かに働きかける
-
沈黙や抑制が感情の封印を表し、観客に深い読解を促す構造になっている
なぜ「良さが分からない」と感じるのか?
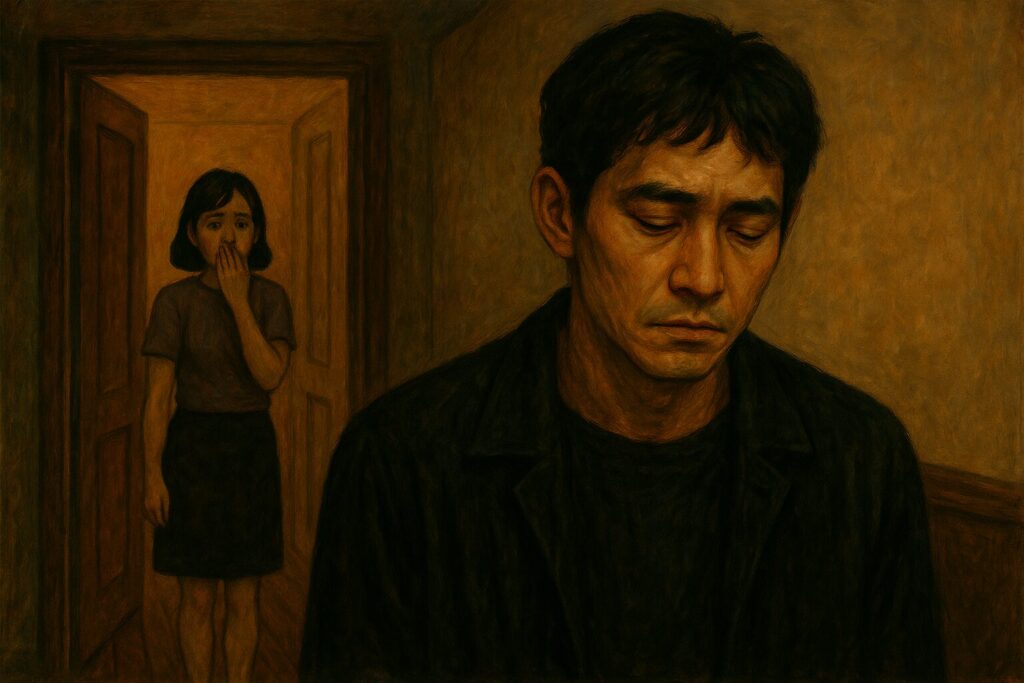
映画の構造が“共感”を遠ざけているから
結論から言えば、『ドライブ・マイ・カー』を観て「良さが分からない」と感じる人は決して少数派ではありません。
その理由のひとつが、従来の物語構造と異なる「感情の起伏の少なさ」や「説明のない空白」が連続するスタイルにあります。
観客の“感情導線”をあえて遮断する演出
多くの映画では、主人公が感情的に爆発したり、状況がドラマティックに展開することで観客の心を引きつけます。
しかし本作では、そうした「わかりやすさ」が意図的に排除されています。
例えば、主人公・家福が妻の浮気を目撃したあとも、彼は何も言わずに部屋を出てしまいます。
普通の映画であれば対峙や修羅場が描かれる場面ですが、ここでは沈黙と無表情で“見て見ぬふり”をするのです。
このように「感情を表に出さない演出」が連続することで、観客は登場人物の心理に共感しづらくなり、物語から距離を感じてしまうのです。
30ページの原作を3時間に引き延ばした理由
この作品の原作は、村上春樹による短編小説『ドライブ・マイ・カー』(『女のいない男たち』所収)で、わずか30ページほど。
しかし、映画ではその短編に他の作品のエッセンスやチェーホフの戯曲『ワーニャ叔父さん』を組み合わせ、3時間近い尺に再構成されています。
これは、濱口竜介監督の「空白で語る」スタイルによるものです。
あえて説明を省き、沈黙や余白に観客の感情を委ねるという挑戦的な手法は、映画的文法としては非常に実験的です。
したがって、従来のハリウッド的テンポや感情描写に慣れた観客には“何も起こっていないように見える”ことが大きな壁となります。
世界的な高評価とのギャップ
ちなみに本作は、カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞し、アカデミー賞では日本映画初の作品賞ノミネートも果たしました(第94回アカデミー賞、2022年)。
Rotten Tomatoesでは98%(批評家評価)、IMDbでも7.6という高スコアを記録しています。
これだけの評価を受けながら「良さがわからない」と感じてしまうのは、観客自身が「映画を観る」という行為に無意識に“期待しているもの”が満たされないからとも言えます。
それでも“わからなさ”に意味がある
このように考えると、「良さが分からない」と思ったとしても、それは観客が間違っているわけではありません。
むしろ、そう感じることこそが、この映画が投げかけている問いなのです。
観終わったあとにモヤモヤが残るという体験こそ、観客に自分の感受性を見つめ直させ、日常を見つめ返すきっかけを与える仕掛けとも言えるでしょう。
「気持ち悪い」の正体を掘り下げる

不安定さと“見えないもの”が不気味さを生む
多くの人が『ドライブ・マイ・カー』を観たあとに感じる「気持ち悪い」という感覚には、物語に潜む“曖昧さ”と“異物感”が大きく関係しています。
結論を先に述べると、この映画の「気持ち悪さ」は、物語的な快楽ではなく、現実の不条理に限りなく近い“説明のつかない世界”を描いているからです。
高槻という人物の存在が不安を増幅させる
岡田将生演じる高槻は、主人公・家福の妻の浮気相手という立場で登場します。
しかし彼は、ただの恋敵というポジションではなく、底知れない闇や狂気を内包する“得体の知れない人物”として描かれます。
たとえば、彼はカメラで盗撮されたことをきっかけに暴力をふるい、後に相手が死亡したことで逮捕されてしまいます。
この出来事も、「なぜここでそんなことが起こるのか?」という説明がほとんど与えられず、観客の不安を置き去りにしたまま物語が進行するのです。
妻・音の語る“物語”が放つ不穏さ
家福の亡き妻・音は、セックスのあとに物語を即興で語るという不思議な習慣を持っていました。
その物語のひとつ「やつめうなぎの少女」は、性的な不穏さと死の匂いを漂わせ、聴いているだけで居心地の悪さを感じさせます。
しかも、その物語の続きを後に高槻が語り出すという構造は、誰が真実を握っているのかが曖昧なまま、観客の感情を揺さぶる不協和音となって響きます。
沈黙・余白・説明のなさが“怖さ”を生む
本作では、何かが起きたときに「何があったのか」「どう感じたのか」を明言するシーンがほとんどありません。
そのため、観客は登場人物の内面を“想像するしかない”状況に置かれます。
この「見えないものに向き合わされる構造」が、人間の本能的な不安や気味悪さを刺激する結果になっているのです。
「気持ち悪さ」は物語の“機能”だった
つまり、ドライブ・マイ・カーにおける「気持ち悪い」という感覚は、演出上の失敗や不快さではなく、物語が本来持っている意図的な“仕掛け”だと言えます。
家福もみさきも、それぞれ過去の傷や後悔から目を背けてきた人物です。
しかし彼らが自分の「見たくない現実」に直面していくことで、物語は少しずつ希望に転じていきます。
そして観客自身も、「説明されない不安」を通じて自分の中にある感情の傷や“未処理の痛み”と向き合うきっかけを得ていくのです。
棒読み演技は本当に下手だったのか?
実は“下手”ではなく、明確な演出手法だった
結論から言うと、『ドライブ・マイ・カー』の“棒読み”のように感じる演技は、演技力の不足ではありません。
濱口竜介監督による意図的な演出スタイルであり、「イタリア式本読み」と呼ばれる手法に基づいたものです。
イタリア式本読みとは何か?
この演出方法は、フランス人映画監督ジャン・ルノワールの影響を受けた手法で、稽古の初期段階で役者に感情を込めず、台詞をただ機械的に読むことから始まります。
その目的は、演技による過剰な感情表現や固定的なキャラクター解釈を避けることにあります。
濱口監督もこの技法を積極的に採用しており、過去作『ハッピーアワー』や『偶然と想像』でも同様の演技スタイルが見られます。
つまり、“棒読み”は監督がテキストを重視し、観客の想像力を引き出すための選択なのです。
棒読みであることで得られる効果
いくら演技がうまくても、感情を前面に押し出した演技は、観客にとって「答えを押し付けられる感覚」を生むことがあります。
それに対して、棒読みのような“演技をしていない演技”は、観客自身が言葉の意味や感情の裏を想像しながら観る余地を与えます。
例えば、家福が俳優たちに「うまく演じる必要はない」と言うシーンがありますが、これはまさに“演じないこと”を通して、台詞の持つ本質を炙り出そうとする試みなのです。
実際の評価と専門家の見解
『ドライブ・マイ・カー』の演技に対しては、国際的にも高い評価が下されています。
米映画レビューサイト《Rotten Tomatoes》では98%(批評家支持率)を記録し、演技に対するレビューも好意的なものが大多数です(出典)。
また、批評家の町山智浩氏はラジオ番組にて、「セリフの棒読みこそが観客に“間”と“余白”を与える。村上春樹の文体と非常に親和性が高い」と述べています。
それでも「違和感」が拭えない理由
ただし、このスタイルには当然ながらリスクもあります。
感情を抑えすぎた演技は、観客によっては「冷たい」「退屈」「感情移入できない」と感じられる可能性があるからです。
つまり、演技力の問題ではなく、“演出の哲学”としての選択である以上、見る側の価値観と噛み合わなければ違和感が生じるのは自然なことです。
違和感の裏にある“意図”を知る価値
このように考えると、棒読みのように聞こえる演技は、むしろ観客に考えさせる余白を与える「しかけ」であるといえます。
「下手だ」と切り捨ててしまう前に、なぜそのように演じられているのかという視点を持つと、作品の見え方は大きく変わるでしょう。
感情が動かないのは“演出”の狙い
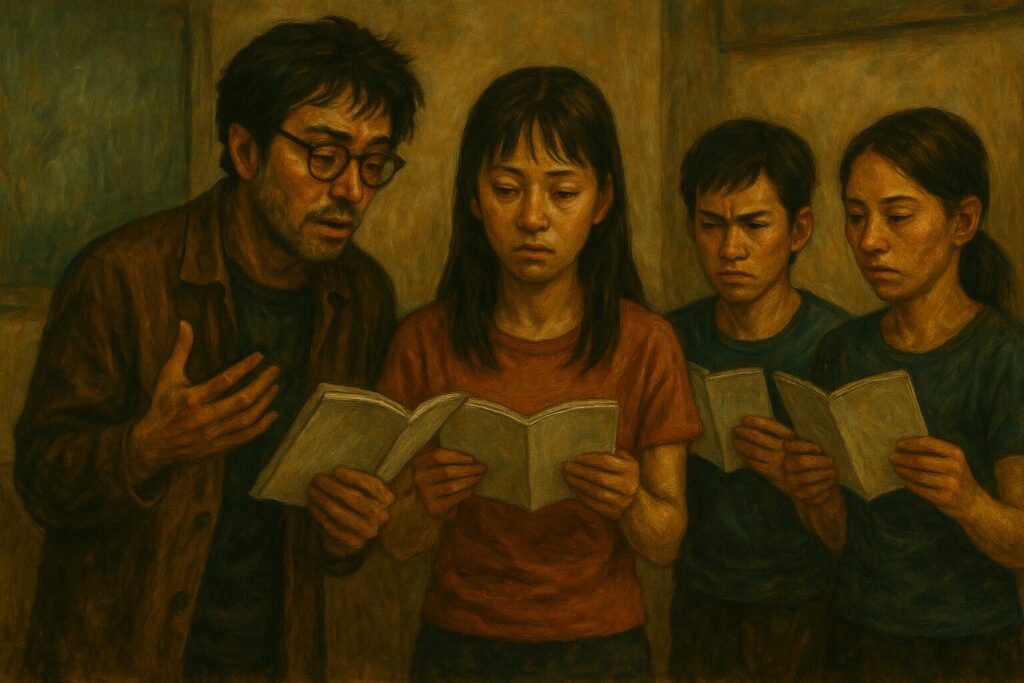
抑制された表現が語る“沈黙の物語”
『ドライブ・マイ・カー』が「感情が動かない」「淡々としていて退屈」と感じられるのは、多くの場面で感情表現をあえて抑制しているためです。
これは、濱口竜介監督が意図的に設計した演出であり、「言葉にできない感情」や「沈黙の重さ」を描くための手法です。
すぐに泣かない。怒らない。語らない。
この作品では、登場人物たちが強い感情を抱えていても、それを表情や声に出して表現することはほとんどありません。
たとえば、家福は妻の死の真実を知っていたにもかかわらず、それを妻に問い詰めることもなく、最後まで黙っていたのです。
この「語らなさ」がもたらす静けさが、観客にとっては感情の動きが伝わってこない=無感動と映ることがあります。
人間の内面に潜るための演出
しかし、この沈黙こそが、濱口監督の狙いです。
「人は、何を語らず、どう沈黙するかに、その人の人生が現れる」と彼は過去のインタビューで語っています。
この演出法は、村上春樹の原作の持つ「説明しない」「感情を避ける」といった特性とも非常に相性が良く、“沈黙の中で再生していく人間の姿”を丁寧に描いているといえます。
“感情の欠如”ではなく“感情の封印”
一見、感情が欠けているように見える登場人物たちは、実は心の底に大きな痛みや葛藤を抱えています。
家福は妻の死に対する後悔を、みさきは母を見殺しにしたという罪悪感を、それぞれの胸の内に隠して生きてきました。
彼らが自らの傷と向き合う過程を、静かに、そして少しずつ描いていくことで、感情が“ゆっくり溶けていく”ような体験が観客にも共有されていくのです。
クライマックスでの“解放”が意味すること
作品後半、家福がみさきの故郷を訪れたシーンでは、それまで沈黙を貫いてきた彼がついに感情を吐露します。
「僕はちゃんと傷つかなかった。だから音を失った」と語る場面は、それまでの抑制された感情がようやく解放された瞬間です。
ここで初めて、抑え込まれていた感情が表に現れ、観客の心を大きく揺さぶります。
観客に“自分の感情”を問う映画
このように、『ドライブ・マイ・カー』は感情を直接的に描かず、観客自身に「あなたはどう感じるか?」を問う構造になっています。
これは非常に高度で、なおかつ難解な手法でもあるため、慣れていないと“無表情な映画”と受け取られてしまうのです。
ただ単に冷たいのではなく、沈黙の中に豊かな感情が流れていることを知ると、映画の印象は大きく変わるでしょう。
「つまらない」の先にある体験とは?
一見“退屈”でも、内面が揺さぶられる映画
『ドライブ・マイ・カー』を観終わって「つまらない」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、その“退屈さ”の裏には、観る人の内面を静かに揺さぶる体験が仕掛けられています。
すぐに盛り上がらない構成
本作は、序盤40分をプロローグのように使い、妻・音の死までを丁寧に描いています。
その後、舞台演出家として広島に赴任する家福が、専属ドライバーのみさきと出会い、静かに物語が進んでいきます。
つまり、ハリウッド映画のような起承転結やスピード感がないため、「何が起きるのか」と身構えたまま、観客は置いていかれるように感じやすいのです。
物語よりも「余白」が主役
ここで重要なのは、本作が「展開」ではなく「感情の余白」を描いているという点です。
日常の車内会話、窓越しの風景、俳優たちの朗読稽古など、一見すると“何も起きていない”時間が続きます。
しかし、そうした無言の時間や淡々とした演出が、鑑賞者の中に眠る感情や記憶を自然と呼び起こす仕掛けになっているのです。
観終わったあとに“じわじわ来る”映画
Filmarksなどのレビューサイトを見ても、「観ている最中は退屈だったが、後から何度も思い返してしまう」「ラストが心に残って離れない」といった声が多く見られます。
このように、本作は「観ている間」よりも「観た後」に効いてくる映画と言えます。
心理学的に言えば、これは「遅延型の情動反応」に近く、意識下でゆっくりと感情が処理されるタイプの作品といえるでしょう。
“つまらなさ”に潜む意味を知る
このように考えると、「つまらなかった」という感想も否定する必要はありません。
むしろ、それはこの映画が観る者に“速効性”ではなく“残響”を与える構造であることを証明しているとも言えるのです。
どれだけ映画に集中しても心が動かないように感じたのなら、もしかするとそこに自分自身の感情が閉じ込められていた可能性もあるかもしれません。
ライブマイカーが気持ち悪いと感じる“わかりにくさ”の正体
チェックリスト
-
説明を省く演出は観客の感性を信頼する姿勢である
-
感情や真意は行間に託され、観客の想像力が求められる
-
わかりにくさは意図された構造であり、“深読みさせるための装飾”ではない
-
受け身の鑑賞では理解が進まず、能動的な読み取りが必要とされる
-
感情を抑制する登場人物の描写は、過去の傷と向き合う姿勢の表現である
-
言葉より沈黙や空間で語る演出が、観客に“心で観る”体験を促している
“観客に委ねる”映画の挑戦とは?
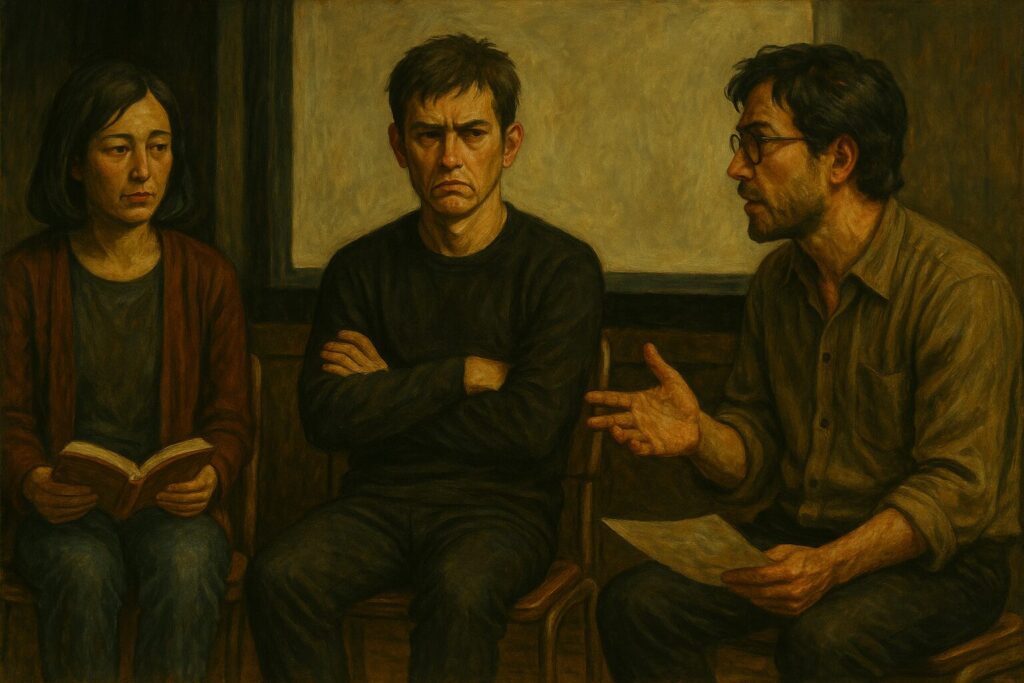
説明をしない=信頼しているという姿勢
『ドライブ・マイ・カー』では、物語の核心部分や登場人物の感情を“説明しない”ことで観客に委ねるという演出が徹底されています。
これは決して不親切なのではなく、「観る人の知性と感受性を信じている」という姿勢の現れです。
台詞の意味を“受け取る側”に任せる構成
例えば、家福と高槻が会話するシーンでは、互いの感情や真意を明言することはありません。
観客はその会話の“行間”を読み、何が語られなかったのか、なぜ言葉を選んだのかを想像しながら向き合うことになります。
こうしたスタイルは、文学や演劇に近く、村上春樹の小説の持つ空気感とも一致しています。
特に「言葉では語れないものをどう伝えるか」というテーマが全編に流れており、観客自身の内面と向き合う時間を与えているのです。
受け身の鑑賞では“何も得られない”作品
一般的な映画では、「ここで泣いて」「ここで驚いて」という明確な誘導があります。
しかし本作では、そうした誘導がありません。
そのため、ただスクリーンを眺めているだけでは、何も伝わってこないように感じてしまうこともあります。
この映画が求めているのは、観客が自ら“読み取ろうとする姿勢”なのです。
演出家・濱口竜介の狙い
濱口監督は「言葉を尽くしても本質にたどり着けないような“こわさ”もある」と語っています(出典:【解説】映画『ドライブ・マイ・カー』対話の“壁”を越える、「言葉」への知的探求|CINEMORE(シネモア))。
濱口監督は一貫して「言葉で説明しすぎない映画作り」を公言しており、説明的にならず観客に考える間や余白を与える演出であるという監督の姿勢が伺えます。
これは演劇稽古のシーンにも表れており、登場人物たちが“言葉だけを淡々と読む”時間が続きます。
感情の表出を抑えた状態で稽古を続けることで、台詞の意味や重みを観客自身が探るよう促しているのです。
委ねられることに意味がある
このように、『ドライブ・マイ・カー』は観る側の解釈によって成り立つ“開かれた作品”です。
正解が用意されていない代わりに、自分なりの答えを持つ自由があります。
わからないままでいい、解釈が揺れていてもいい――
そう思えるようになったとき、はじめてこの映画の核心に触れることができるのではないでしょうか。
わかりにくさ=深読みの余地ではない
“難解”という印象が生まれる背景
『ドライブ・マイ・カー』を観て「わかりにくい」と感じる人は少なくありません。
物語の展開は静かで、台詞は断片的、感情も抑制され、演出意図が見えづらい場面も多いからです。
しかしここで重要なのは、その「わかりにくさ」が観客の深読みを誘うための“装飾”ではないという点です。
表現の曖昧さは「装飾」ではない
たとえば、音が残した未完の物語や、高槻の謎めいた台詞、沈黙のまま交わる家福とみさきの関係など、明確な説明はほとんどされません。
この曖昧さが「芸術的すぎて理解できない」と距離を感じさせる原因になっているのです。
ただし、これらは演出上の“気取り”ではなく、「説明しすぎないこと」が物語構造の一部として機能していることが特徴です。
観客を受け身にしないための手法
濱口竜介監督はかねてより「観客の感性や思考に委ねる映画づくり」を明言しており、2021年の日経新聞のインタビューでフィクションとドキュメンタリーの境界についてこう述べています。(出典:Ryusuke Hamaguchi - Wikipedia)
“To some extent, all films are fiction and documentary at the same time.”
この発言は、映画が現実を「写すだけ」のものではなく、ある種の“俳優のリアル”を記録するメディアだという認識を示しており、言葉に頼りすぎない映像表現への志向を端的に示す言葉です。
つまり、物語の断片性や言葉の省略は、観る側の感性を信頼して“読み取らせる”ための構造的意図なのです。
“謎解き型”ではないという理解
一方で、あえて断言しますが、『ドライブ・マイ・カー』は“深読み”を促す推理劇ではありません。
キャラクターの行動に隠された謎を解くような作りではなく、「わからないものと、どう向き合うか」という姿勢自体を描いている作品です。
だからこそ、「意味不明」や「難解すぎる」という拒絶反応が起きても不思議ではありません。
わからないままでも“正解”
映画評論家の野村雅夫氏は、「ドライブ・マイ・カーを観て“わからない”と感じたなら、その感覚はすでに映画と深く接している証だ」と述べています。
これはまさに、“理解ではなく共鳴”を求める映画の本質を突いた言葉です。
何かを完全に把握しようとするのではなく、「わからなさ」と共存する姿勢こそが、本作の真の味わい方と言えるでしょう。
なぜ登場人物が“感情を隠す”のか
抑圧こそが、キャラクターを形づくっている
本作の登場人物たちは、一貫して感情を表に出さない描かれ方をしています。
怒らず、泣かず、愛しているとも言わず、ただ静かに沈黙する場面が多いのです。
この特徴は、彼らが感情を持っていないからではありません。むしろ逆で、強すぎる感情を抱えているからこそ、それを外に出せずに抑圧しているのです。
家福・音・みさき――それぞれの「傷」
たとえば家福は、妻が不倫していたことを知りながら、それを問いたださず沈黙を選びました。
その後も、喪失と向き合わず“再生”の過程を停滞させたまま演出の仕事に没頭します。
みさきも同様に、母の死に対する罪悪感を一切語ろうとせず、車内でも必要最低限の会話にとどめています。
これらの描写は、感情の欠如ではなく「自らの傷に向き合う勇気が持てない人々の姿」なのです。
感情を“隠す”ことで描かれるリアル
心理学的にも、人は過去のトラウマや大きな喪失体験を抱えると、それを防衛するために「感情を遮断」することがあります。
このメカニズムを反映した演出こそが、『ドライブ・マイ・カー』の抑制された会話と演技です。
そして、それが結果として観客に「何も伝わってこない」と感じさせる大きな要因になっています。
セリフに頼らず、“空気”で伝える
濱口監督は、感情を説明する台詞を極力排除する演出家です。
彼は「言葉にできない感情のほうが人間には多い」とし、言葉にならない沈黙や視線の揺らぎに感情の本質を見出そうとします。
この演出方法は、現代のハイテンポな映像作品に慣れた観客には、物足りなさや距離感を覚えさせるかもしれません。
“語らないこと”こそが核心に迫る手段
しかし、その“語らなさ”の中にこそ、キャラクターたちの本当の感情が宿っています。
例えば、クライマックスで家福が「ちゃんと傷つかなかった」と独白する場面は、それまで隠されていた彼の感情がようやく言葉になる瞬間です。
それまでの沈黙があったからこそ、この短い一言が圧倒的な説得力を持って胸に響くのです。
車内が語る、もう一つの物語

静かな車内は“対話”の場ではなく“心”の揺らぎの場
映画『ドライブ・マイ・カー』において、もっとも象徴的な空間のひとつが「赤いサーブ900」の車内です。
一見するとただの移動手段にすぎないこの空間ですが、物語が進むにつれ、それは登場人物の“内面”を映すもう一つの舞台へと変貌していきます。
車という密室が生む“緊張と解放”
本作における車内は、リラックスできる空間であると同時に、逃げ場のない“密室”でもあります。
たとえば、家福と専属ドライバーみさきが交わす会話の多くは、まさにこの車内で起こります。
自宅や稽古場といった生活の延長線ではなく、お互いに“顔を見ずに語れる”横並びの関係性が、彼らの心を少しずつほどいていくのです。
また、走行中の微かな車の揺れやエンジン音、窓越しの景色が、沈黙すらも意味ある“間”として成立させる装置となっています。
このような環境だからこそ、普段なら押し殺してしまう感情が、ほんの少しだけ顔を出すことが可能になるのです。
沈黙がつなぐものは、言葉ではない
たとえば、家福とみさきが一言も交わさないまま走るシーンでは、沈黙自体が感情のやりとりを担っているようにも見えます。
この“言葉にしない対話”は、濱口竜介監督の演出手法のひとつであり、観客に想像と共鳴を促す巧みなしかけです。
監督は『Drive My Car』についてのインタビューで以下のように述べています(出典:Ryûsuke Hamaguchi on Adapting Murakami with Drive My Car and the Sound of Silence)
“Silence has to be understood as another form of communication. … Later in the movie, when there is some silence, it is now a different silence. It’s become another way of communicating.”
これは「沈黙は(ただの無音ではなく)別のコミュニケーション手段」として用いられ、物語における沈黙の層が深まることを指摘しており、「無言で過ごす時間にこそ人間の輪郭がにじむ」という信念が伺えます。
サーブ900は「音との対話の遺産」
音が録音した戯曲のセリフを、家福が何度も再生しながら練習する車内のシーンも印象的です。
そこでは、“過去の音”と“今の家福”が、車内という私的空間を介して向き合い続けている構図が成り立っています。
つまり、この赤い車は単なる乗り物ではなく、登場人物が過去と向き合い、感情を整理し、心を再構築する「心の劇場」として機能しているのです。
韓国ラストに違和感を覚えたあなたへ

突然の舞台転換――意図された「余白」
物語の終盤、物語は舞台を韓国・釜山に移します。
この場面転換に対して、「なぜ唐突に韓国なのか?」「雰囲気が変わってついていけなかった」と違和感を抱いた方も多いかもしれません。
ただし、この“韓国ラスト”には明確な意味があります。それは、再生・移動・決別といった本作の核心テーマを象徴する転地としての機能です。
過去の喪失から未来へ“サーブ”される
注目すべきは、みさきが家福の車を受け継いでいる点です。
彼女は釜山の市場で食材を買い、飼い犬とともに穏やかな日々を過ごしているように見えます。
この描写は、彼女自身が過去の罪と向き合い、家福から“心のバトン”を受け取った象徴的な場面と読み取ることができます。
タイトルの“サーブ”=車の名前(Saab)と、テニスの「サーブ=再スタートの一打」を掛けたとも解釈でき、新たな人生への一歩を踏み出す隠喩が仕込まれているのです。
なぜラストは“家福”ではなく“みさき”なのか
通常であれば、主人公である家福の再生を見届けて物語を締めるところでしょう。
しかし本作は、あえて脇役だったみさきをラストショットの中心に据えることで、「癒しの主導権は彼女に託された」と伝えています。
米誌 Vanity Fair は、作品の評価記事(出典:The Lifelike Triumph of ‘Drive My Car’ | Vanity Fair)で以下のように述べています。
“Misaki grew as a character … Eventually, she became almost like a protagonist in the film.”
これは、みさき役の三浦透子が物語を通じて明確に成長し、実質的にもう一人の主役として機能しているとの評価です。彼女の静かなる存在感が、家福と並ぶほど重要な役割を果たしているとしています。
ラストの余韻が問いかけるもの
一方で、ラストに強く感情を揺さぶられたというより、「静かにフェードアウトするような感覚だった」という声も多く聞かれます。
この感覚は、まさに『ドライブ・マイ・カー』らしさそのものです。
つまり、決定的な感動ではなく、観る人の中に「何かが残る」ように設計された結末なのです。
違和感を否定せずに受け入れる
違和感を覚えたあなたの感性は正しいものです。
ただ、その違和感の正体を一度深掘りしてみると、登場人物の再出発や癒しといった静かなテーマに気づく“余白”がそこにあったと気づくかもしれません。
正解より、心で感じてほしい映画
最初にピンとこなかったあなたへ
『ドライブ・マイ・カー』を観終えて、「正直、よくわからなかった」「退屈で感情移入できなかった」と感じた方もいるでしょう。
それは決して感受性の問題でも、映画を理解する力の欠如でもありません。むしろこの作品は、“すぐに腑に落ちる”ことを目的としていない映画だからです。
すぐに答えをくれない映画もある
本作の監督・濱口竜介氏は、「満足できる終わりにせず、少し壊すことで余白を残したかった」と語っています(出典:Saab Story: Ryusuke Hamaguchi’s Driving Emotions • Journal • A Letterboxd Magazine • Letterboxd)。
つまり、作り手が一方的に感動や理解を押しつけるのではなく、受け取る側が“自分自身と向き合う中で気づく”ことを期待しているのです。
これは、たとえば絵画のように、観た瞬間の印象では理解できなくても、時間をおいてふと思い出したり、誰かとの会話の中で意味が浮かび上がってくる、そんな性質に近いかもしれません。
あなたの「分からない」は自然な感覚
映画レビューサイト「Filmarks」でも、星3以下のレビューに共通して「感情が動かない」「演技が不自然に感じた」「長く感じた」といった声が散見されます。
これは本作が、あえて説明や感情表現を抑えた“間”の演出を多用しているためです。
こうした不親切さに戸惑うのは当然のことですし、それでもいいのです。
大切なのは、その違和感が「観ることを止める理由」ではなく、「もう一度確かめたいと思うきっかけ」になるかどうかなのです。
再鑑賞がもたらす新しい気づき
多くの鑑賞者が「2回目でようやくわかった」と語っています。
1回目では“退屈”に見えたシーンが、実は登場人物の感情の揺らぎや心の傷を丁寧に描いたものだったと気づく。
あるいは、みさきの言葉に、家福との深い関係性がにじんでいたと後から分かる——そうした“気づき”が再鑑賞によって自然と生まれるのです。
再び観るときは「心の耳」を澄ませて
もしもう一度観るなら、「理解しよう」と肩肘を張らず、感情の動きや登場人物の沈黙の意味に“心で耳を傾ける”ような視点を意識してみてください。
演劇の読み合わせ、車中での無言の時間、語られない過去――それらはすべて、人生の痛みや赦しを「音ではなく、静けさ」で語る映画的挑戦の一部です。
そして、“あなたの物語”と重ねてみる
『ドライブ・マイ・カー』は、喪失・赦し・再生という普遍的なテーマを描いています。
誰しもが人生のどこかで味わう感情を、抽象化せず、そのまま丁寧に提示している点で、ある意味「個人的な体験」と重ねることができる稀有な作品です。
だからこそ、今は響かなかったとしても、1年後、何かを失ったとき、あるいは立ち直ろうとしたときに、ふと思い出す映画になるかもしれません。
無理に好きにならなくてもいい
重要なのは、「良さをわかろうとすること」ではなく、自分の感覚を否定しないことです。
あなたが感じた違和感やつまらなさも、映画との大切な出会い方のひとつ。
だからこそ、無理に好きになる必要はありません。
ただ、もし心に少しでも“ひっかかり”が残っているなら、
もう一度だけ、「理解する」のではなく、「感じる」視点で観てみてください。
その時、静かに何かが変わるかもしれません。
ドライブマイカーが気持ち悪いと感じる理由の総括
- 静けさが続き緊張感が解けず不安になる
- 感情を抑えた演技が冷たく映る
- 棒読みのようなセリフが不自然に感じられる
- 高槻の人物像に生理的嫌悪を覚える
- 心理描写が少なく登場人物の意図が読みづらい
- 無音や沈黙が多く落ち着かない雰囲気になる
- 会話が淡々としていて感情移入しにくい
- 車内の密室感が息苦しさを与える
- 韓国のラストシーンが唐突に映る
- 結末がはっきりせず消化不良感を抱く
- 長尺のわりに展開が乏しく退屈さを感じる
- 難解なセリフ回しが距離を生む
- 感情表現が乏しく共鳴できない
- 登場人物同士の関係が掴みにくい
- 深読みを求められる構成が負担になる