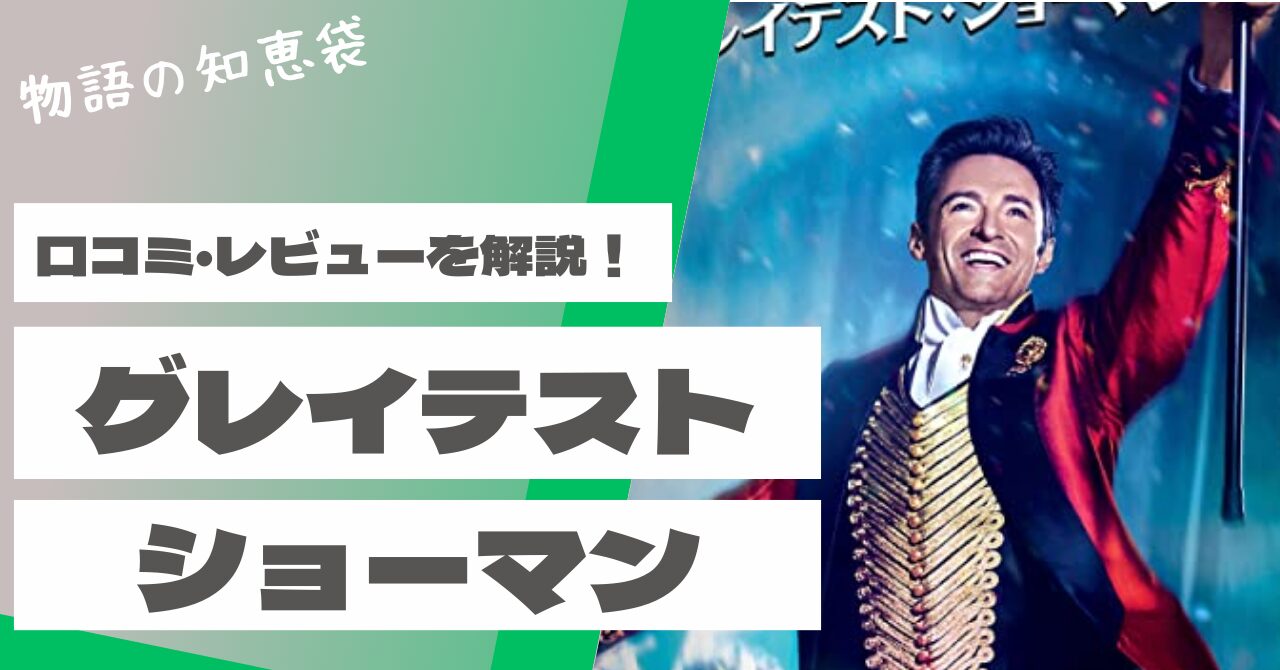『グレイテスト・ショーマン』は、華やかな音楽と感動的なストーリーが魅力のミュージカル映画ですが、視聴者の評価は大きく分かれており、「好き」と絶賛する声がある一方で「嫌い」と感じる人も少なくない。特に、P.T.バーナムの実話をもとにした物語でありながら、史実とは異なる描写に対する批判が目立つように見受けられました。また、音楽は圧倒的に評価される一方で、ストーリー展開やキャラクター描写には疑問の声が上がることもしばしば。今回の記事では、『グレイテスト・ショーマン』の「好き」「嫌い」の両意見を踏まえ、その評価が分かれる理由を徹底解説していきます!
映画のストーリーがどのように史実と異なるのか、より詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。
『グレイテスト・ショーマン』のあらすじと実話に隠された真実
グレイテスト・ショーマンは好き嫌いが分かれる?魅力と評価の賛否
チェックリスト
- 『グレイテスト・ショーマン』は音楽やビジュアルが高く評価される一方、物語には賛否がある
- 高評価の理由は感動的な楽曲、華やかな映像、前向きなメッセージ
- 中評価の理由はストーリーの浅さや登場人物の掘り下げ不足
- 低評価の理由は史実との乖離や「見世物小屋」の描写の違和感
- 音楽やパフォーマンスを楽しむエンタメ作品として観るのが最適
- 史実や社会的メッセージに期待すると物足りなさを感じることがある
『グレイテスト・ショーマン』は本当に名作?賛否の理由を徹底解説
『グレイテスト・ショーマン』は、2017年に公開されたミュージカル映画で、音楽やビジュアルの美しさが話題となりました。しかし、その評価は一様ではありません。ここでは、映画の評価を「高評価」「中評価」「低評価」の3つに分類し、各意見の特徴を解説します。
『グレイテスト・ショーマン』の評価の内訳
多くのレビューを参考にした結果、以下のような評価の傾向が見られます。
- 高評価:約60%
- 中評価:約25%
- 低評価:約15%
全体として、約6割の観客が好意的に評価しており、特にエンタメ性を重視する層に人気があります。
高評価の理由|音楽とビジュアルの圧倒的な魅力
多くの観客が絶賛したのは、以下の点です。
- 心を揺さぶる楽曲:「This is Me」や「Never Enough」といった楽曲が感動を誘い、登場人物たちの心情が見事に表現されていると評価されています。
- 華やかな映像とダンス:鮮やかな衣装やダイナミックなパフォーマンスが、ミュージカル映画としての魅力を最大限に引き出しています。
- 前向きなメッセージ:「夢を追い続けること」「多様性の大切さ」など、希望に満ちたストーリーが共感を呼びました。
中評価の理由|音楽の良さは認めつつ、物語には疑問の声
中立的な立場の意見としては、次のような点が挙げられます。
- 物語の浅さ:「音楽は素晴らしいが、ストーリーの展開が早すぎて感情移入しにくい」という声が多く見られました。
- 登場人物の掘り下げ不足:「サーカス団員の背景があまり描かれておらず、感情移入しづらい」という意見が目立ちます。
低評価の理由|史実との乖離や描写の違和感
一部の観客からは、次のような批判が寄せられています。
- 史実との違い:「P.T.バーナムの実像とはかけ離れすぎている」「実際のバーナムは利益優先で、映画のような理想的な人物ではなかった」という指摘があります。
- 「見世物小屋」の描写:「差別的な見世物を美化しすぎている」との批判があり、特に社会的メッセージに期待した観客には不満が残ったようです。
『グレイテスト・ショーマン』の物語と史実の違いについて、さらに詳しく解説した記事はこちら。
『グレイテスト・ショーマン』のあらすじと実話に隠された真実
総評|『グレイテスト・ショーマン』はどう楽しむべき?
『グレイテスト・ショーマン』は、エンタメ作品として音楽や映像を楽しむ視点で観るのが最もおすすめです。実話や社会的メッセージを深く追求したい人には物足りない部分があるかもしれませんが、華やかさや感動的な楽曲に心を動かされる作品として、多くの観客の心をつかんだのは間違いありません。
音楽は絶賛!でもなぜ物語には賛否が?
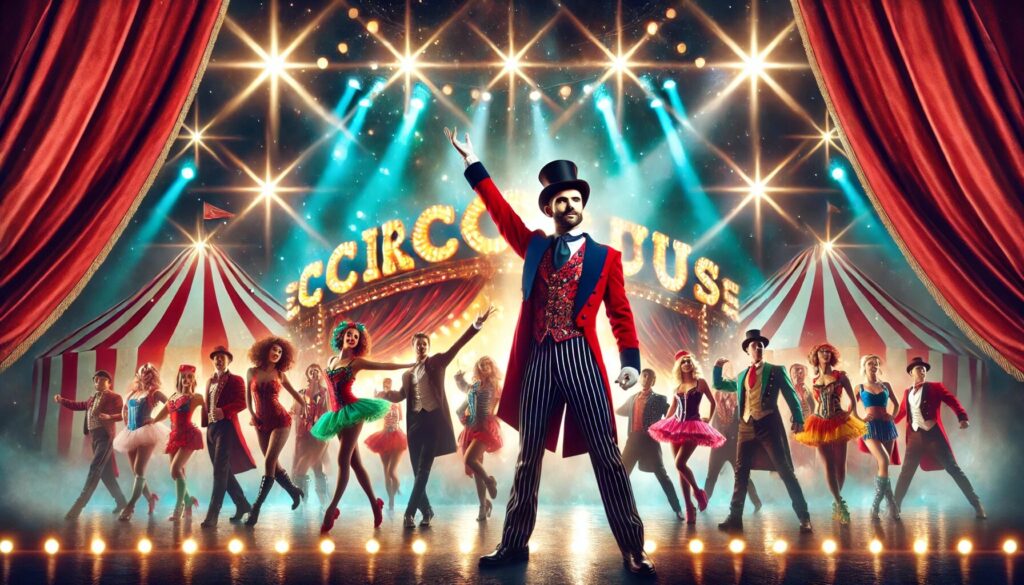
『グレイテスト・ショーマン』は、音楽が特に高く評価された作品ですが、物語に関しては意見が分かれました。その理由を具体的に見ていきましょう。
音楽が絶賛された理由
『グレイテスト・ショーマン』の音楽は、以下の3点が特に評価されています。
- 感情を引き出す歌詞:「This is Me」は、自己肯定感や誇りをテーマにした歌詞が共感を呼び、世界中の人々に愛されています。
- 迫力あるパフォーマンス:楽曲とシンクロしたダンスや演出が、ミュージカルとしての完成度を引き上げています。
- 耳に残るメロディー:「Never Enough」や「Rewrite the Stars」など、印象的なメロディーが観客の心に強く残る楽曲が多数含まれています。
これらの音楽は、映画を見終わった後も余韻として残るほどのインパクトを持ち、映画の魅力の大部分を支えていると言っても過言ではありません。
物語に賛否が分かれた理由
一方で、物語については以下のような指摘があります。
- 史実と大きく異なる:主人公P.T.バーナムの実像は、映画のような理想的な人物ではなく、利益優先の興行師だったという史実があります。これにより、「映画が事実を歪めている」との批判がありました。
- サーカス団員の描写の不足:物語の中で、個性的なサーカス団員たちの背景や葛藤が十分に描かれていないため、感情移入しにくいと感じる観客もいました。
- 展開の速さとご都合主義:バーナムの失敗から成功への道筋があまりにスムーズすぎて、リアリティに欠けると指摘する声もあります。
観る人によって感じ方が変わる作品
『グレイテスト・ショーマン』の音楽は、幅広い層に受け入れられ、特にミュージカルファンや音楽を重視する観客に強く支持されています。
一方で、物語に対しては「フィクションとして割り切れば感動的だが、史実に基づいた作品としては不満が残る」といった意見が多く見られます。
『グレイテスト・ショーマン』のおすすめの楽しみ方
この作品は、「音楽」と「パフォーマンス」を楽しむミュージカル映画として鑑賞するのがベストです。物語に過度な期待を持つと評価が分かれる可能性がありますが、ビジュアルや音楽の魅力を感じたい人には強くおすすめできる作品です。
「嫌い」と言われる理由は?批判の声を深掘り検証
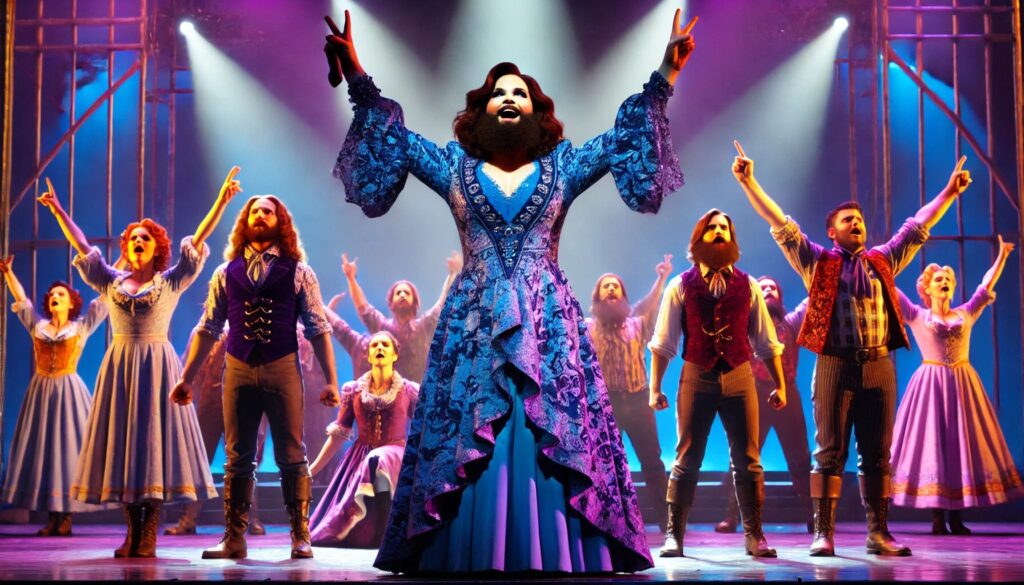
『グレイテスト・ショーマン』は多くの観客に感動を与えた一方で、「嫌い」と感じる人がいるのも事実です。ここでは、その理由について具体的に解説します。
批判1:史実との乖離が大きい
『グレイテスト・ショーマン』はP.T.バーナムの実話をベースにした映画ですが、事実とは大きく異なる描写が多くあります。映画では、バーナムは「個性豊かな人々を救い、舞台で輝かせた理想の人物」として描かれていますが、実際のバーナムは利益を優先するビジネスマンの側面が強かったと言われています。
特に、映画の中で描かれた「見世物小屋」については、社会的に弱い立場の人々を興味本位で見世物にしたという側面が指摘されています。映画はポジティブに描かれていますが、歴史的な観点から見るとバーナムの行為は「搾取」だと感じる人も少なくありません。このため、史実を重視する人からは「美化しすぎ」との声が上がっています。
批判2:物語が「ご都合主義的」に感じる
映画の展開は非常にテンポがよく、華やかな音楽と映像で進行します。しかし、苦難や葛藤のシーンが短く描かれ、困難があっさりと解決する展開が気になるという意見もあります。例えば、バーナムが仲間や家族とのすれ違いを乗り越える場面は、深刻な問題が短時間で解決するため「現実感が薄い」と感じる人もいるようです。
批判3:「多様性の象徴」というメッセージに違和感
映画では、外見や個性に特徴のあるサーカス団員が「自分らしさを誇りに思う」という強いメッセージが描かれています。これは感動的なテーマではありますが、一部の人からは「結局は見世物として利用されている」という否定的な意見も見られます。特に、現代の価値観で見ると、差別的な描写に感じるという声が上がることもあります。
批判4:音楽と映像の華やかさが「軽い」と感じる人も
『グレイテスト・ショーマン』は、鮮やかな映像と感動的な音楽が大きな魅力です。しかし、その華やかさがかえって「内容が薄く感じる」という意見もあります。特に、深刻なテーマが描かれているはずの場面でも、明るい音楽が流れることで、問題が軽く扱われている印象を受ける人もいます。
まとめ
『グレイテスト・ショーマン』が「嫌い」と感じる人の多くは、史実との違いや、ご都合主義的なストーリー展開に違和感を持つ傾向があります。特に、実在の人物や社会的なテーマに興味がある人にとって、物語の描かれ方が納得できないと感じることが多いようです。それでも、音楽や映像の魅力に引き込まれ、多くのファンを獲得している点は見逃せません。
「史実と違う」との指摘、その背景にある事実とは
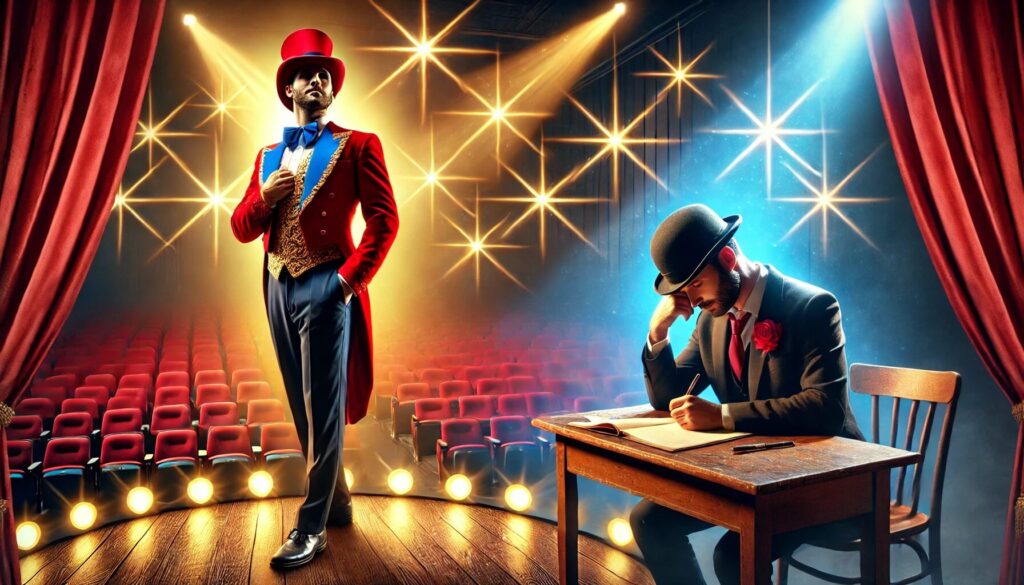
『グレイテスト・ショーマン』はP.T.バーナムの人生を描いた作品ですが、実際の歴史とは異なる点が数多くあります。ここでは、具体的にどの部分が史実と異なるのかを解説します。
バーナムの人物像の違い
映画では、P.T.バーナムは「貧しい家庭から夢を追い、成功をつかんだ感動的な人物」として描かれています。実際のバーナムも貧しい家庭で育ったことは事実ですが、利益追求のために誇張や虚偽の宣伝を多用した野心的なビジネスマンとしての一面もありました。
映画では「社会的に弱い立場の人々に光を当てた」と描かれていますが、実際には興味本位の「見世物」として集客していた側面が強いと指摘されています。そのため、「バーナムが人々の尊厳を守った英雄」として描かれている点に違和感を持つ人も少なくありません。
サーカス団員の描写の違い
映画では、サーカス団員たちは「多様性の象徴」としてポジティブに描かれています。しかし、史実では「異形の人々」として見世物にされ、好奇の目にさらされる存在として扱われていました。映画のように「自信を持って輝く存在」として尊重されていたわけではない点は、事実と異なる部分です。
ジェニー・リンドとの関係
映画では、オペラ歌手のジェニー・リンドはバーナムに好意を寄せる人物として描かれています。しかし、実際のジェニー・リンドとバーナムの関係はビジネスパートナーとしてのつながりが強く、恋愛関係の描写は創作です。さらに、リンドが歌う「Never Enough」は劇中の印象的なシーンですが、ジェニー・リンド自身がこの楽曲を歌った事実はありません。
バーナムの家庭の描写
映画では、バーナムと妻チャリティの関係が「身分違いの恋愛」として描かれていますが、実際にはチャリティも一般的な家庭で育ち、映画のような身分の差は存在しませんでした。バーナムとチャリティは実際には比較的平凡な家庭生活を送っていたとされています。
「見世物小屋」の実態
映画の中では、バーナムが「人々の個性を輝かせるための舞台」として見世物小屋を運営したと描かれています。しかし、実際には差別や偏見を利用した興行として、現代では批判の対象になる側面もありました。バーナム自身は「観客の好奇心を満たす」ために、障害者や身体的に特徴のある人々を利用したとの指摘もあります。
まとめ
『グレイテスト・ショーマン』は史実をベースにしつつも、感動的なエンターテイメント作品として再構築されたフィクション要素が強い作品です。映画は「多様性の尊重」や「夢を追う大切さ」を描いていますが、実際のP.T.バーナムが行った行為には、現代の価値観では問題視される点も含まれています。そのため、映画を観る際は、史実と創作の違いを理解した上で楽しむのが最適でしょう。
エンタメ作品としての魅力と物足りなさの違いとは?

『グレイテスト・ショーマン』は、華やかな音楽や映像、感動的なストーリーが特徴のエンターテイメント作品です。しかし、観る人の視点によっては「物足りなさ」を感じるという意見もあります。ここでは、その魅力と物足りなさの違いについて解説します。
魅力1:圧倒的な音楽と映像美
『グレイテスト・ショーマン』の最大の魅力は、圧巻の音楽とビジュアルの華やかさです。特に、劇中の名曲「This is Me」や「Never Enough」は、登場人物たちの感情を強く伝え、観客を感動の渦に引き込みます。さらに、ダンスシーンやサーカスの演出は色彩豊かで、視覚的にも楽しめる仕上がりになっています。これにより、観終わった後の余韻が心地よいと感じる観客が多いです。
魅力2:シンプルなストーリーで感動しやすい
物語は「夢の実現」や「家族の大切さ」という普遍的なテーマが軸になっています。これにより、難解な要素がなく、幅広い世代が共感しやすいストーリーとなっているのが魅力です。サーカス団員たちが「ありのままの自分を受け入れる」という強いメッセージも、現代社会において響く内容です。
魅力3:ポジティブなメッセージとエネルギー
本作は、全体を通じて前向きなエネルギーに満ちています。特に、サーカス団員が「自分らしさ」を誇りに思い、堂々とステージに立つ姿は、自己肯定や多様性の大切さを強く訴えかけています。これにより、鑑賞後に「明日から頑張ろう」と背中を押される作品として支持される声も多くあります。
物足りなさ1:史実と異なる描写
一方で、歴史を知る人や事実にこだわる人からは、「美化しすぎ」「事実と異なる」という指摘が目立ちます。映画では、P.T.バーナムは理想的な人物として描かれていますが、実際には利益を優先する一面もあったため、「実際のバーナムとは違いすぎる」と感じる人もいます。
物足りなさ2:葛藤や困難の描写が薄い
物語はテンポが良い反面、困難や葛藤のシーンが短く、あっさりと解決するという印象を与える場合があります。特に、バーナムが家族や仲間との関係に悩む場面は、深刻な問題であるにもかかわらず、簡単に解決してしまう展開が「ご都合主義的」と指摘されることがあります。
物足りなさ3:社会的メッセージの描写が曖昧
映画では「多様性の尊重」というメッセージが語られていますが、同時に「外見に特徴のある人々を見世物として扱った」史実が背景にあるため、現代の価値観で見ると問題点が気になるという意見もあります。特に、差別や偏見といった社会問題の描写は浅く、リアリティに欠けると感じる人も少なくありません。
まとめ
『グレイテスト・ショーマン』は、華やかな音楽や映像を楽しみたい人にはピッタリのエンタメ作品です。一方で、史実や社会問題について深く考えたい人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。観る人の価値観や期待するポイント次第で、印象が大きく変わる作品だと言えるでしょう。
「夢と現実のギャップ」をどう受け止めるべきか?

『グレイテスト・ショーマン』は、「夢を追う素晴らしさ」と「現実の厳しさ」の両方が描かれた作品です。ここでは、作品が示した「夢と現実のギャップ」について解説します。
映画が描いた「夢」の象徴
映画では、P.T.バーナムが「誰もが輝ける舞台を作りたい」という強い信念を持ち、社会の片隅にいた人々と共にショーを成功させる姿が描かれています。これは、「夢を追い続ければ、困難があっても実現できる」というメッセージとして映像に落とし込まれています。
特に、楽曲「A Million Dreams」は、バーナムの幼少期の貧しい生活の中で、「いつか夢を叶えたい」という強い願望を表現した感動的なシーンです。このシーンは、「夢を持つことの大切さ」を象徴しています。
映画が描いた「現実」の厳しさ
一方で、映画の中では「夢を追う代償」として、家族や仲間との関係がすれ違い、孤独や挫折を味わうシーンが描かれています。バーナムは成功を目指すあまり、家族や仲間をないがしろにし、結果的にすべてを失う危機に直面します。これは、夢を追う過程で直面する現実の厳しさを象徴しています。
ギャップを埋めるための「気づき」
映画のクライマックスでは、バーナムが「最も大切なのは家族の笑顔」と気づき、夢だけでなく現実の大切さを再認識します。この場面では、「夢を追う過程でも、現実を無視してはいけない」というメッセージが強く込められています。
「夢と現実」のギャップに対する視聴者の受け止め方
観客の視点によって、このギャップに対する印象は異なります。
- 夢に向かって挑戦する人にとっては、バーナムの姿が「夢を追う勇気」を与えてくれるでしょう。
- 現実的な視点を持つ人にとっては、バーナムの成功や葛藤が「理想と現実の乖離」を象徴し、現実の厳しさを痛感するかもしれません。
まとめ
『グレイテスト・ショーマン』は、夢を持つことの大切さと、その過程で直面する現実の厳しさの両方を描いた作品です。どちらの側面を重視するかによって、映画から感じ取るメッセージは変わるでしょう。観る人が自身の経験や考え方と照らし合わせることで、より深く物語を味わうことができます。
『グレイテスト・ショーマン』のあらすじや史実との違いを深掘りした記事もおすすめです。
『グレイテスト・ショーマン』のあらすじと実話に隠された真実
グレイテスト・ショーマンは好き嫌いが分かれる?評価が分かれるワケ
チェックリスト
- 「見世物小屋」の描写は「差別的」と「多様性の象徴」の2つの視点で評価が分かれる
- 差別的な視点では、身体的特徴のある人々を興味本位で見世物にしたビジネスモデルが問題視される
- 多様性の象徴としての評価では、サーカス団員が自らの個性を誇る姿が描かれた点が支持される
- 主人公バーナムは映画では理想的な人物として描かれたが、史実では利益優先のビジネスパーソンだった
- ジェニー・リンドの「Never Enough」は名声や富の虚しさと人間的な孤独を象徴する
- 『グレイテスト・ショーマン』は、視点次第で評価が変わるエンターテインメント作品として捉えられている
「見世物小屋」の描写は差別?それとも多様性の象徴?

『グレイテスト・ショーマン』における「見世物小屋」の描写は、視聴者の視点によって「差別」と「多様性の象徴」という2つの評価に分かれています。ここでは、それぞれの視点に基づいた意見を解説します。
「差別的」と指摘される理由
映画では、P.T.バーナムが「社会の片隅で生きる人々」を集め、サーカス団として見世物にする場面があります。これが一部の視聴者からは「差別的」と批判される理由となっています。
- 外見を“見せ物”にしたビジネスモデル
バーナムは、身体的特徴が目立つ人々や障害を持つ人々を舞台に立たせ、その個性を「異様なもの」として宣伝する手法を取りました。現代の価値観では、この行為は「他人の容姿を興味本位で消費している」と受け取られやすく、差別的と感じる人が多いです。 - 実際の「フリークス・ショー」の問題点
史実では、バーナムが行った「見世物小屋」は“奇妙な人々”を好奇の目で集めるビジネス手法だったとされています。彼が「多様性を尊重した」というよりも、「他者の外見を利用して利益を得た」と解釈されることがあるため、映画を美化しすぎていると批判されることもあります。
「多様性の象徴」としての評価
一方で、本作では「見世物小屋」に登場する人々が、自らの個性に誇りを持ち、堂々と人前に立つ姿が描かれています。これが「多様性の象徴」として評価される理由です。
- 自己肯定感の回復
劇中では、社会から冷たい目を向けられたサーカス団員たちが、「自分はこのままでいい」と気づき、誇りを取り戻していきます。特に、楽曲「This is Me」は「ありのままの自分を受け入れる」強いメッセージが込められており、多くの人々に感動を与えました。これが「多様性を称える作品」として高く評価された理由です。 - 偏見に立ち向かう力強さ
映画では、団員たちが「自分たちは人と違うが、それが個性であり誇りだ」と堂々と舞台に立つ姿が印象的です。これにより、彼らは「自らの価値を自覚し、差別に屈しない」という力強いメッセージを体現しています。
どちらの視点が正しいのか?
『グレイテスト・ショーマン』は、史実に基づきつつも、現代の価値観を意識して再構築されたエンターテイメント作品です。そのため、差別的な要素があると感じる人と、多様性を称える作品と感じる人がいるのは自然なことです。観る人の価値観や視点によって、印象は大きく変わるでしょう。
まとめ
『グレイテスト・ショーマン』の「見世物小屋」は、過去の社会が抱えていた「差別的な視点」を映し出している一方で、現代の「多様性を受け入れる姿勢」を反映した側面もあります。どちらの視点で見るかによって、物語の解釈は大きく異なるため、「どのようなメッセージを感じ取るか」は観る人次第と言えるでしょう。
主人公バーナムは本当に“理想の人物”だったのか?

映画『グレイテスト・ショーマン』では、主人公P.T.バーナムが「夢を追い続ける理想の人物」として描かれています。しかし、史実と比較すると「実際のバーナムは異なる人物だった」という指摘もあります。ここでは、映画と史実の違いを解説し、バーナムが本当に「理想の人物」だったのかを検証します。
映画におけるバーナムの描写
映画のバーナムは、貧しい幼少期から努力で成功を掴み取り、家族や仲間のために奮闘する「誠実な人物」として描かれています。観客に感動を与えるために努力を惜しまず、サーカス団員たちに光を当てる姿は「人々を幸せにするエンターテイナー」としての理想像を体現しています。
史実におけるバーナムの人物像
一方で、実際のバーナムは、商才に長けた「ビジネスパーソン」としての側面が強く、「宣伝の父」とも称される人物でした。彼は、話題性のあるパフォーマンスを追求するために、誇張や虚偽の宣伝を行うこともありました。
- 「見世物小屋」を興行として利用
実際のバーナムは、「社会の片隅で生きる人々を支えた」というよりも、「話題性のある存在として売り出した」側面が強いです。彼は、個性豊かな団員たちに生活の場を与えたものの、その動機にはビジネス的な意図もあったと考えられています。 - 家族との関係や価値観
映画では、バーナムは家族を何より大切にする人物として描かれていますが、史実では「事業の成功」に重きを置き、家庭を顧みなかった時期もあったとされています。この点が、映画が「美化しすぎ」と指摘される理由の一つです。
バーナムの「理想の人物像」とは?
映画のバーナムは、「理想の人物」として描かれていますが、これは史実に基づきつつも、物語のメッセージを強めるためのフィクション要素が加えられた結果です。実際のバーナムは、成功のためには手段を選ばない側面があり、必ずしも「理想の人物」とは言えません。しかし、「人々を笑顔にしたい」という純粋な信念は、事実に基づくものです。
まとめ
映画のバーナムは、「理想的なヒーロー像」を強調するために誇張されたキャラクターですが、根底にある「人々を楽しませたい」という信念は、実際のバーナムの価値観に近いものです。観る人が「理想的な人物」として受け止めるか、「商才に長けたビジネスマン」として捉えるかによって、バーナムの評価は大きく変わるでしょう。
ジェニー・リンドの役割と「Never Enough」の真の意味

『グレイテスト・ショーマン』に登場するジェニー・リンドは、物語の重要な転機を担うキャラクターです。彼女の役割と、劇中で披露される楽曲「Never Enough」には、物語のメッセージが強く反映されています。ここでは、ジェニー・リンドの役割と「Never Enough」の持つ真の意味について解説します。
ジェニー・リンドの役割とは?
ジェニー・リンドは、スウェーデン出身の実在したオペラ歌手です。映画では、バーナムが成功をさらに拡大するために起用した「完璧な歌姫」として描かれています。彼女の役割は、単に「バーナムのビジネス成功の象徴」ではなく、バーナム自身の価値観や人生の方向性に影響を与える存在として重要です。
- 名声と成功の象徴
ジェニーは、社会的に成功し、称賛される存在としてバーナムの理想を体現するキャラクターです。彼女の登場は、バーナムが「さらなる成功」を求め、サーカス団の仲間や家族を後回しにする転機となります。ジェニーの存在が、バーナムの野心と誤った選択を浮き彫りにしています。 - 孤独と空虚感の象徴
映画の中でジェニーは「名声を得ても心は満たされない」という孤独な一面を持っています。表面的には完璧な歌姫として称賛されながらも、心の奥では満たされない葛藤を抱えており、その内面が「Never Enough」に表現されています。
「Never Enough」に込められた真の意味
「Never Enough」は、ジェニーが劇中で披露する力強くも切ないバラードです。華やかな舞台で圧倒的な歌声を披露し、多くの喝采を浴びるシーンですが、その歌詞には名声や富では埋められない「内面の孤独」が込められています。
- 虚無感と欲望の象徴
歌詞の中には、「無数のスポットライトがあっても、決して満たされない」という言葉が登場します。これは、成功や名声を得ても「本当に求めているもの」は手に入らないという意味を示しています。ジェニーが欲していたのは「人としての愛」や「心のつながり」であり、それが叶わない切なさが「Never Enough」のメッセージです。 - バーナムとの関係を示唆
劇中では、ジェニーがバーナムに特別な想いを抱いている様子が描かれています。しかし、バーナムの心が家族や仲間にあると気づいたジェニーは、孤独を深めていきます。その感情が「Never Enough」を通して伝わることで、ジェニーの「愛の欠如」と「人間的な弱さ」が浮き彫りになります。
「Never Enough」が伝えるメッセージ
「Never Enough」は、「外側の成功だけでは人は幸せになれない」という教訓を伝えています。名声や富があっても、真に大切なのは「愛やつながり」だということを、映画のクライマックスに向けて印象付ける楽曲です。
まとめ
ジェニー・リンドは、物語の中で「成功の象徴」でありながら「内面の孤独」を抱えたキャラクターとして描かれています。彼女の存在と「Never Enough」という楽曲は、バーナムが「本当に大切なもの」に気づくための重要な要素となっています。成功や名声を求める過程で、何を見失ってはいけないのかを観る者に問いかけるシーンと言えるでしょう。
「This is Me」に共感する人としない人、その違いとは?
『グレイテスト・ショーマン』の名曲「This is Me」は、多様性や自己肯定をテーマにした力強い楽曲として話題となりました。多くの人々に感動を与えた一方で、一部の視聴者には響かなかったという声もあります。ここでは、「This is Me」に共感する人としない人の違いについて解説します。
「This is Me」に共感する人の特徴
「This is Me」に共感する人は、楽曲に込められた「自分の個性を誇りに思う」というメッセージに心を動かされる傾向があります。
- 過去に劣等感を感じた経験がある人
社会の偏見や差別に直面し、自信を失った経験がある人は、「This is Me」に強く共感します。特に、映画の中でサーカス団員たちが「隠れて生きるのではなく、堂々と生きる」と決意する場面は、自己肯定感を取り戻したいと願う人々に勇気を与えています。 - 自己表現に葛藤を感じている人
「人と違う自分を受け入れる」ことに悩んでいる人にとって、「This is Me」の歌詞は強い励ましになります。楽曲の「私はこのままでいい」というメッセージは、自信を持ちたいと願う人にとって共感しやすい内容です。 - 多様性を尊重する価値観を持つ人
「This is Me」は、社会の枠にとらわれず、多様な人々がそれぞれの個性を誇るべきだという強いメッセージを伝えています。多様性の重要性に共感する人は、楽曲に深く共鳴する傾向があります。
「This is Me」に共感しない人の特徴
一方で、「This is Me」に共感できないと感じる人もいます。その理由には、以下の要因が考えられます。
- 自己肯定の必要性を感じない人
すでに自分に自信があり、自己肯定感を確立している人は、「This is Me」に共感しにくいことがあります。彼らにとって「堂々と生きる」メッセージは、既に実践していることとして響かない場合があります。 - 映画の描写に不自然さを感じた人
「This is Me」の場面は、映画のクライマックスに向けて感情が高まる重要なシーンです。しかし、一部の視聴者には「急に自己肯定が強調されすぎている」と感じられ、感情移入しにくいといった意見も見られます。 - 現実とのギャップに違和感を持つ人
「This is Me」は理想を強調した楽曲であり、現実には社会の偏見や差別に簡単に立ち向かえないケースも多いです。そのため、楽曲の力強いメッセージに「現実とは異なる」と感じる人もいます。
「This is Me」はどんな人に響くのか?
「This is Me」は、特に「自分らしさを取り戻したい」と感じている人に強く響く楽曲です。逆に、すでに自信を持って行動できている人や、楽曲の理想主義的な側面に違和感を持つ人には、共感しにくいといえます。
まとめ
「This is Me」は、多様性や自己肯定を称える強いメッセージソングとして評価されています。共感するかどうかは、視聴者の人生経験や価値観に大きく影響されるため、受け取り方は人それぞれです。「自分の個性をどう受け入れるか」を考えさせられるこの楽曲は、幅広い層の心に響く力強い応援歌として、多くの人々に愛され続けています。
視点次第で変わる『グレイテスト・ショーマン』の評価

『グレイテスト・ショーマン』は、その視点によって評価が大きく分かれる作品です。音楽やビジュアルの魅力を称賛する声がある一方で、物語や史実との違いに対する批判も見られます。ここでは、評価が分かれる主な理由と、それぞれの視点について解説します。
映像美と音楽に注目した視点
映画を「エンターテイメント作品」として観る視点では、ビジュアルの華やかさや音楽のクオリティが高く評価されています。
- 華やかな演出と迫力のあるパフォーマンス
『グレイテスト・ショーマン』は、舞台のような臨場感と派手な演出が特徴です。特に、オープニングの「The Greatest Show」やクライマックスの「From Now On」では、観客を一気に引き込むエネルギッシュな演出が高評価を得ています。 - 感情を揺さぶる楽曲の力
「This is Me」や「Never Enough」など、楽曲はそれぞれのキャラクターの内面を表現しており、聴く者の心に強く響きます。音楽の魅力を重視する視点では、作品全体の完成度が非常に高く評価されています。
史実との違いに注目した視点
一方で、「史実と違う」という点を重視する視点では、物語の展開やバーナムの描かれ方に批判的な意見があります。
- バーナムの美化された描写
実際のP.T.バーナムは、利益を優先し「フリークス・ショー」として障害のある人々を見世物にしていた側面があります。しかし、映画では「多様性を称える人物」として理想的に描かれており、これに対して「事実をねじ曲げている」と感じる人も少なくありません。 - 社会問題の軽視
差別や偏見の問題が描かれているものの、登場人物たちが前向きに立ち上がる様子が強調されており、問題の本質が軽視されていると指摘する声もあります。
メッセージ性に注目した視点
「多様性」「夢を追いかける大切さ」などのメッセージ性に焦点を当てる視点では、作品が持つ希望や勇気を与える力が評価されています。
- 「This is Me」に象徴される自己肯定のメッセージ
「自分はこのままでいい」と誇りを持つ姿が描かれ、多くの視聴者に勇気を与えています。このメッセージは、LGBTQ+や社会的マイノリティの人々にも強く支持されています。
まとめ
『グレイテスト・ショーマン』の評価は、「何を重視するか」で大きく変わります。エンタメとしての魅力を楽しむ人には好意的に受け入れられる一方、史実や社会的課題を重視する人には違和感が残るかもしれません。視聴する際は、どの視点で作品を見るかを意識することで、より深く楽しめるでしょう。
グレイテスト・ショーマンの評価と好き嫌いが分かれる理由のまとめ
- 音楽や映像美は圧倒的で高評価を得ている
- 「This is Me」や「Never Enough」などの楽曲が感動を誘う
- 華やかな演出とダイナミックなダンスが魅力
- 夢や多様性をテーマにしたポジティブなメッセージが共感を呼ぶ
- ストーリーの展開が早く、感情移入が難しいと感じる人がいる
- サーカス団員の描写が浅く、背景が描かれないと指摘される
- 史実と大きく異なり、P.T.バーナムの美化が批判されている
- 「見世物小屋」の描写が差別的と感じる人がいる
- ジェニー・リンドとバーナムの関係は史実とは異なる創作要素が強い
- バーナムの成功や挫折がご都合主義的に描かれていると指摘される
- 「多様性の象徴」として評価される一方で、問題の本質が軽視されているとの声もある
- エンタメ作品として観ると魅力が際立つが、史実に期待すると物足りなさが残る
- 視点次第で評価が大きく分かれる作品である
- ミュージカルファンや音楽重視の観客には特に好評
- 社会問題や史実に関心がある人には不満が残ることがある