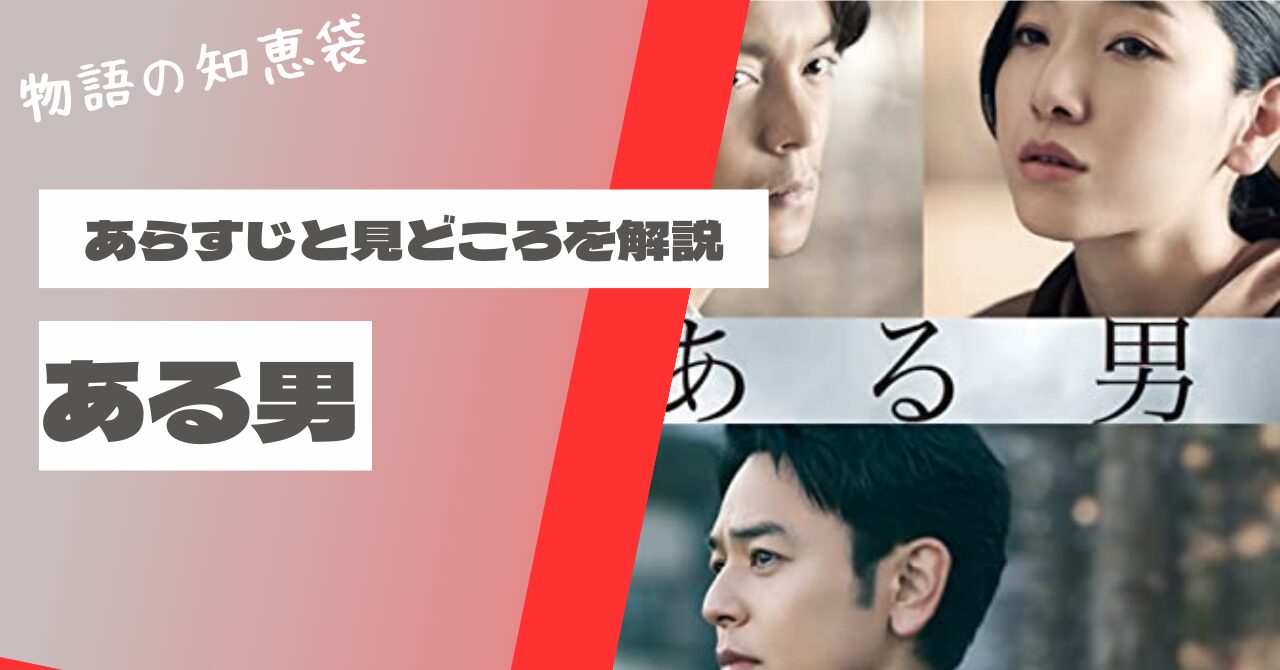映画『ある男』は、愛した人が「別人」だったという衝撃の事実から始まるサスペンス・ヒューマンドラマであり、複雑な人間模様と深いテーマ性が話題となった作品です。物語は、主人公の城戸弁護士が依頼を受け、亡くなった男性の正体を追ううちに、偽りの人生の真相に迫っていくというあらすじで展開される。さらに、映画終盤のラストでは「13歳の子供」という言葉が登場し、物語全体に隠された真のメッセージに気づかされる印象的なシーンとして考察していく。加えて、城戸弁護士の苦悩をより深める要素として、彼の妻の浮気相手の存在が描かれており、家庭の崩壊や孤独が彼の葛藤に大きく影響している。『ある男』は、単なるミステリーではなく、「本当の幸せとは何か?」を問いかける作品として、見る者の心を強く揺さぶる物語に仕上がっているため、その魅力を本記事で紹介します!
また、映画『ある男』は、その深いテーマと複雑なストーリー展開から、観る人によって評価が大きく分かれます。実際に『つまらない』と感じる声があるのも事実です。そんな評価の実態や理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。→ 映画『ある男』のレビュー検証|つまらないと評価された理由とは?
『ある男』考察とあらすじ解説|ネタバレありで深掘り分析
チェックリスト
- 映画『ある男』は、他人の戸籍を利用して生きる男性の切ない人生を描いたサスペンス・ヒューマンドラマ
- 主人公の城戸弁護士は、在日韓国人3世としての葛藤や妻の浮気問題に苦しむ人物として描かれる
- 原誠は「死刑囚の息子」という過去から逃れるため、他人の戸籍を利用して新たな人生を生きた
- ラストシーンでは、城戸が「伊香保温泉の旅館の次男です」と名乗り、「別人としての人生」を一瞬だけ疑似体験する
- 物語は「名前や戸籍ではなく、築いた絆や愛こそが家族の本質」というメッセージを伝える
- 映画では、差別や偏見の厳しさに対する警鐘と、人は自分自身の生き方で価値が決まるという力強いメッセージが込められている
映画『ある男』基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | ある男 |
| 原作 | 平野啓一郎『ある男』 |
| 公開年 | 2022年 |
| 制作国 | 日本 |
| 上映時間 | 121分 |
| ジャンル | サスペンス・ヒューマンドラマ |
| 監督 | 石川慶 |
| 主演 | 妻夫木聡、安藤サクラ、窪田正孝 |
映画『ある男』は、平野啓一郎の同名小説を原作とし、2022年に公開されたサスペンス・ヒューマンドラマ作品です。監督は『愚行録』や『蜜蜂と遠雷』などで知られる石川慶が務め、繊細かつ力強い演出が話題となりました。主演には妻夫木聡、安藤サクラ、窪田正孝など、日本を代表する実力派俳優がキャスティングされています。
映画『ある男』の基本情報
- 原作:平野啓一郎『ある男』
- 監督:石川慶
- 公開日:2022年11月18日
- 主演キャスト:
- 妻夫木聡(城戸弁護士 役)
- 安藤サクラ(谷口里枝 役)
- 窪田正孝(原誠 / 偽の谷口大祐 役)
- 仲野太賀(本物の谷口大祐 役)
- 柄本明(戸籍ブローカー 役)
- 清野菜名(本物の谷口大祐の恋人・美涼 役)
- 真木よう子(城戸の妻 役)
映画『ある男』のあらすじ(概要)
物語は、夫が事故で亡くなった後に発覚した衝撃の事実から展開します。妻・里枝(安藤サクラ)が愛したはずの夫「谷口大祐」は、実はまったくの別人だったのです。彼は「原誠」という名で、殺人犯の息子という過去を隠すために他人の戸籍を利用し、「谷口大祐」として生きていました。
弁護士・城戸(妻夫木聡)は、里枝からの依頼でこの不可解な事件を調査しますが、物語が進むにつれて、城戸自身が抱える在日韓国人3世としての葛藤や、妻の浮気問題が描かれ、複雑な人間模様が浮き彫りになります。
映画『ある男』のテーマと見どころ
『ある男』は、単なるサスペンス映画ではありません。物語の根底には、「人のアイデンティティ」や「社会の偏見」が深く絡み合っています。原誠が他人の戸籍を利用した背景には、父親が死刑囚であるという出自がありました。彼はその事実に苦しみ、戸籍交換という選択をしたのです。
また、城戸弁護士は自身の在日韓国人としての出自に対して心の葛藤を抱えており、他人になりすまして生きる「原誠」との対比が物語の核心を突いています。さらに、ラストシーンの解釈や、城戸の行動の真意も、観客に深い余韻を残します。
評価と受賞歴
映画『ある男』は、深いテーマ性とキャストの卓越した演技により、第46回日本アカデミー賞最優秀賞をはじめ、多くの映画賞で評価されました。特に、窪田正孝の静かな悲しみを表現する演技と、妻夫木聡の内に秘めた苦悩の演技が高く評価されています。
あらすじ完全ネタバレ解説
映画『ある男』は、他人の人生を背負いながらも本当の愛や家族の意味を描いた、切なくも考えさせられる作品です。物語は複雑な戸籍交換や人間関係が絡み合い、観る者の心を深く揺さぶる内容となっています。ここでは、物語の流れを時系列に沿って詳しく解説します。
映画の導入 - 幸せな家族の崩壊
物語は、主人公の城戸弁護士(妻夫木聡)が、依頼人の谷口里枝(安藤サクラ)から「亡くなった夫の正体を調べてほしい」という奇妙な依頼を受けるところから始まります。里枝は再婚相手の谷口大祐(窪田正孝)と幸せな家庭を築いていましたが、大祐は不慮の事故で命を落とします。
法要の日、久しぶりに訪れた大祐の兄が「この遺影の人物は弟ではない」と告げ、衝撃の事実が判明します。つまり、里枝が再婚して共に暮らした「谷口大祐」という男は、実はまったくの別人だったのです。
調査の進行 - 偽りの人生の真相
城戸弁護士は、戸籍交換の経緯を調べるために各地を訪れ、関係者の証言を得ながら徐々に真相を明らかにしていきます。調査を進めるうちに、大祐として暮らしていた男の正体は「原誠」という別人であることが分かります。原誠は、父親が死刑囚であるという重い過去を抱え、その事実に苦しみながら生きてきました。
原誠は自分の顔が殺人犯の父親に似ていることで、世間からの視線や差別に耐えかね、精神的に追い詰められていました。何度も自殺未遂を繰り返し、最終的に戸籍交換ブローカーを通じて名前を変え、新たな人生をスタートさせたのです。
本物の谷口大祐の存在
一方、調査の中で本物の「谷口大祐」(仲野太賀)も登場します。彼は実家の温泉旅館に生まれ、家族との不仲や人生に行き詰まる思いから、自らの戸籍を捨てる決断をしました。これにより、原誠が「谷口大祐」という身分を手に入れるきっかけとなったのです。
本物の谷口大祐は、行方不明のまま苦しい生活を送っており、戸籍交換によって平穏を得ることができると考えていました。つまり、どちらの人物も自らの過去や家族との関係に苦しみ、逃避するために「別人として生きる道」を選んでいたのです。
里枝の苦悩と愛の本質
真相を知った里枝は、「自分が愛した人が別人だった」という事実に動揺します。しかし、彼女は「夫が原誠であろうと谷口大祐であろうと、彼と過ごした3年9ヶ月の幸せは本物だった」と気づきます。これにより、名前や過去よりも、共に築いた時間や絆こそが家族の本質であるというメッセージが描かれています。
ラストシーン - 城戸弁護士の葛藤
物語のクライマックスでは、城戸弁護士自身もまた葛藤を抱えていたことが浮き彫りになります。彼は在日朝鮮人3世として生まれ、社会的な偏見や差別に苦しんできました。さらに、妻の浮気や義理の両親との不和など、家庭内の悩みも重なり、自らの存在意義を見失いかけていました。
ラストシーンでは、城戸がバーで「私は伊香保温泉の旅館の次男です」と、偽りの身分を語る場面があります。これは、原誠や谷口大祐と同じく、別の人生に憧れた城戸が一瞬だけ「他人の人生」を疑似体験する行為だったのです。彼は実際に戸籍を変えたわけではありませんが、「本当の自分とは何か」を模索する苦悩が見事に表現されています。
映画『ある男』が伝えたメッセージ
映画『ある男』は、「本当の自分とは何か」「人は他人として生きることで幸せになれるのか」という重厚なテーマを描いています。名前や戸籍という形式的なものではなく、共に過ごした時間や愛情が本当の家族の証であるというメッセージが、観る者に深い感銘を与えます。
また、在日朝鮮人や犯罪者の家族という、本人の意思ではどうにもならない「出自」が人の人生にどれほど重くのしかかるのかという社会的な問題にも踏み込み、差別や偏見の根深さを痛感させられる作品となっています。
物語は「名前を変えただけでは人は変われない」という厳しい現実を突きつけつつ、それでもなお「人と人が築く愛情や信頼こそが本質である」と希望を示して終わります。映画『ある男』は、切なくも希望に満ちたメッセージを込めた感動的な物語として、観る人の心に強く残るでしょう。
原誠の動機を深掘り考察|なぜ他人に成りすました?
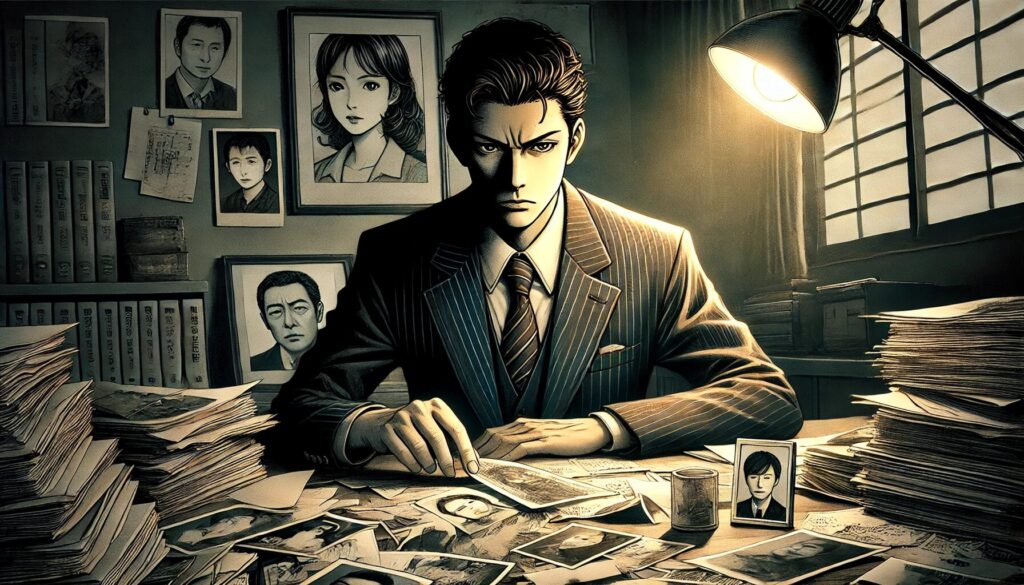
原誠が他人になりすました理由は、父親が死刑囚であるという過去に深く関係しています。彼は自らの出自に苦しみ、自分の人生をリセットするために「他人として生きる道」を選びました。以下では、原誠がなぜ他人の戸籍を利用してまで人生をやり直そうとしたのか、その背景を詳しく考察します。
原誠が背負った「死刑囚の息子」という十字架
原誠の父親は、残忍な殺人事件を起こした死刑囚です。世間からは「殺人犯の息子」というレッテルを貼られ、彼自身は父親の罪とは無関係であるにもかかわらず、重い偏見や差別に晒され続けました。
幼少期から施設で育った原誠は、母親の姓に変えた後も「死刑囚の息子」という事実が周囲に知られてしまい、再び辛い思いをすることになります。社会の冷たい視線に耐えきれず、彼は心身ともに追い詰められていきました。
自らの容姿に対する苦悩
原誠にとってさらに辛かったのは、自分の顔が父親と酷似していたことです。彼は鏡に映る自分の姿が父親を思い起こさせることで、強烈な自己嫌悪に苛まれていました。顔が似ているというだけで「自分も父親のような人間ではないか」という不安や恐れに苦しみ、何度も自殺未遂を繰り返します。
「別人として生きる」選択の背景
原誠はこうした状況から逃れるため、戸籍交換ブローカーを通じて「曽根崎」という名を手に入れ、別人として生きようとしました。しかし、その新たな人生でも平穏は得られませんでした。次第に再び精神的に追い詰められ、最終的には「谷口大祐」という名前に変えて宮崎へ移り住みます。
彼はそこで林業に携わりながら、谷口里枝(安藤サクラ)と出会い、幸せな家庭を築くことになります。原誠にとって「谷口大祐」としての暮らしは、初めて心の平穏を得られた時間だったのです。
原誠の選択が示すもの
原誠の人生は、「戸籍を変えればすべてが変わる」という単純な逃避行動ではなく、社会からの差別や偏見に追い詰められた結果の、やむを得ない選択だったといえます。彼が「谷口大祐」としての4年間で築いた家族との穏やかな時間は、彼にとって唯一の救いでした。
映画『ある男』では、原誠が「自分は原誠ではなく、谷口大祐として生きたい」と願うのではなく、「原誠としては幸せに生きられなかった」という苦しい現実に向き合いながら、他人にならざるを得なかった切ない決断が描かれています。彼の人生は「本当の自分とは何か?」というアイデンティティの葛藤を突きつける、胸を打つ物語です。
仲野太賀(本物の谷口大祐)の動機を考察|戸籍交換の理由

本物の谷口大祐(仲野太賀)が戸籍を捨てた理由は、家族との不和や自らの人生に対する行き詰まりが大きく関係しています。彼は「逃げる」という選択をすることで、自らの過去から解放されようとしました。ここでは、その背景と心理を掘り下げます。
実家との確執と家庭内の問題
本物の谷口大祐は、老舗温泉旅館の次男として生まれました。しかし、旅館の跡継ぎである兄との関係は良好ではなく、家業に対しても嫌悪感を抱いていました。さらに、父親への生体肝移植のドナーになるかどうかを巡る家族内の対立が決定的な溝を生みました。
手術のリスクや自身の将来を考えた結果、谷口大祐はドナーになることを拒否。その決断が家族の怒りを買い、彼は家庭内で孤立してしまいます。これにより、彼は「自分の存在は家族にとって厄介者だ」と思い込むようになったのです。
「自分の人生をやり直したい」という願い
家庭内の問題に加え、谷口大祐は「老舗温泉旅館の次男」という肩書きから解放されたいという願望も抱えていました。家族の期待や過去のしがらみから距離を置くため、彼は新たな人生を求めて「戸籍を交換する」という決断を下します。
谷口大祐は、「自分の人生はこのまま続けても良くならない」という絶望感に駆られ、他人の戸籍を手に入れることが最善の選択だと考えました。彼は最終的に「曽根崎」という名前に変え、姿を消します。
戸籍交換の結果
戸籍を交換して「曽根崎」となった谷口大祐の人生は、決して順調ではありませんでした。彼は貧困に苦しみ、孤独に苛まれながら後悔の念を抱き続けていました。
本物の谷口大祐が「美涼(清野菜名)にもう一度会いたい」と漏らしていたのは、彼が家族や自らの過去に向き合い、本当の意味での「再生」を願っていたからです。これは、戸籍を変えて他人として生きることが、必ずしも幸福をもたらさないという厳しい現実を突きつけています。
谷口大祐の選択が示すもの
谷口大祐が「曽根崎」としての生活に苦しんだ姿は、「戸籍を変えることで過去を消し去ることはできない」という現実を象徴しています。映画では、原誠と対照的に「逃避ではなく、自分の過去や関係を見つめ直すことが本当の解決につながる」というメッセージが込められています。
谷口大祐が選んだ「戸籍交換」という行動は、自らの存在価値を模索しながらも、過去のしがらみを乗り越えようとする苦しい選択だったのです。彼の行動は、「人は名前や立場ではなく、どのように生きるかが重要である」という、映画のテーマに深くつながっています。
城戸弁護士の葛藤と正体

映画『ある男』に登場する城戸弁護士(妻夫木聡)は、物語の核心に迫る重要なキャラクターです。彼の存在は、原誠や谷口大祐が抱えていた「自らのアイデンティティへの葛藤」を象徴しつつ、現代社会が抱える差別問題の縮図でもあります。ここでは、城戸弁護士の人物像と彼が抱えていた葛藤について解説します。
城戸弁護士の正体|在日コリアン3世という背景
城戸弁護士は、在日コリアン3世として日本社会に生きてきた過去を持っています。彼は帰化して日本国籍を取得し、日本人としての生活を送っていました。しかし、城戸自身は「帰化した」という事実が完全に自分の出自を消し去るものではないと感じています。
在日コリアン3世というアイデンティティは、城戸の人生に深い影を落としていました。彼の義父(妻の父)は城戸を婿として受け入れているものの、内心では差別意識を抱えており、嫌味とも取れる発言が散見されます。城戸はその態度に対して表立って反論することができず、黙って受け入れる姿が印象的です。これは、社会的な成功や家族という安定のために、自らのアイデンティティを押し殺してきた苦しみを象徴しています。
妻との関係悪化が抱えた孤独
さらに、城戸は妻の浮気に悩まされており、私生活でも深い孤独を抱えていました。彼が築いた「安定した生活」も、妻との関係の崩壊によって揺らいでいきます。表面的には家庭があるように見えても、城戸はその居場所に満たされず、孤独を感じ続けていたのです。
原誠への共感と自己投影
城戸が原誠の人生に強くのめり込んだのは、彼自身の葛藤と深くリンクしていたためです。原誠は「死刑囚の息子」という偏見から逃れるために別人として生きる道を選びましたが、城戸自身も「在日3世」という出自を消し去るように帰化し、他人の人生を演じるように生きていました。城戸は原誠の苦悩を追いかける中で、「自分は本当の自分として生きられているのか?」という疑問に向き合うようになります。
ラストシーンで見せた「別人になる願望」
映画のラストシーンでは、城戸がバーで隣の男性に対して「自分は伊香保温泉の老舗旅館の次男だ」と話す場面が描かれます。これは原作小説では物語の前半に配置されていたエピソードですが、映画ではラストに据えることで、「城戸自身が戸籍を変え、別人として生きることを選んだのか?」という印象的な余韻を残しています。
このシーンは、城戸が実際に戸籍を交換したのか、それとも一時的に「他人になった自分」を楽しんでいただけなのか、観る人によって解釈が分かれる部分です。いずれにしても、「自分を偽らなければ生きにくい」という葛藤を抱え続けた城戸の苦しみが色濃く表れています。
城戸弁護士が象徴する「自分とは何か」という問い
城戸の姿は、「自らの出自や過去が、今の自分にどのような影響を与えているのか?」という普遍的なテーマに直結しています。彼が在日3世としての生い立ちに苦しみながらも、日常生活ではその事実を隠し、誰にも打ち明けられない葛藤を抱え続ける姿は、映画『ある男』が描く「本当の自分とは何か?」という問いの象徴的な存在です。
差別表現の意図とメッセージ

映画『ある男』では、いくつかの場面で差別的な表現が登場します。これは作品のテーマを際立たせる意図的な演出であり、現代社会が抱える根深い問題を浮き彫りにしています。ここでは、映画における差別表現の意味と、そこに込められたメッセージを解説します。
映画で描かれた差別表現
映画内では、以下のシーンが差別表現として印象に残る部分です。
- 小見浦(柄本明)が「在日(朝鮮人)は見ればすぐわかる」と発言する場面
- 城戸の義父が、城戸に対して皮肉を込めた差別的な言動を見せる場面
- TVで放映されるヘイトスピーチの集会を見て、城戸が強く動揺する場面
これらのシーンは、差別が日常の一部として根付いてしまっている現実を象徴しています。特に、「在日コリアンである」という出自は、本人の努力では変えられない事実でありながら、その一点だけで差別や偏見にさらされる」という理不尽さが強く描かれています。
差別表現の意図とメッセージ
こうした差別的な描写は、決して不快感を与えるためではなく、「無意識の偏見がいかに社会に浸透しているか」を伝えるための重要な演出です。城戸弁護士のように、成功を手に入れ、家庭を築いているにもかかわらず、「在日」というレッテルから逃れられない現実が描かれています。これは、どれだけ社会的に認められても、「過去は消せない」という現実の厳しさを突きつけています。
また、原誠が「死刑囚の息子」として差別を受け続け、社会から逃れようとした姿は、「人は生まれながらの環境を選べない」という理不尽さを痛烈に描いています。この差別問題は、現代社会でも根強く存在しており、映画はそうした問題を観客に問いかけています。
差別に向き合うための重要なメッセージ
映画『ある男』が伝えたかったのは、単なる被害の悲惨さではなく、「人は他者の過去や出自ではなく、その人自身と向き合うべきだ」という普遍的なメッセージです。城戸が原誠の人生に共感し、最後に「他人になりたい」という思いを抱いたのは、「自分がどんな人間であるかは、社会や他人に決めつけられるべきではない」という信念の表れでもあります。
この映画は、「生まれや過去に左右されず、人は自分自身の生き方で価値が決まる」という力強いメッセージを通して、偏見や差別の不条理に対する警鐘を鳴らしています。
『ある男』ラストの考察をネタバレ解説|戸籍変更の真相と謎
チェックリスト
- 城戸弁護士の妻の浮気は、彼のアイデンティティの葛藤や家庭の不安定さを象徴する重要な要素
- 映画では「遠山淳一」が浮気相手の可能性として示唆されるが、確定情報ではない
- 映画版では、原作よりも城戸の妻の浮気や家庭の崩壊が強調され、彼の苦悩が深く描かれる
- 城戸はラストシーンで「伊香保温泉の旅館の次男」と名乗るが、これは実際の戸籍変更ではなく、別人としての生き方への一時的な憧れを示している
- 「13歳の子供」というセリフは、城戸が原誠の築いた幸せな家庭に対する羨望や願望を象徴している
- 映画のラストでは、「名前や過去ではなく、今を大切に生きることが本当の幸せである」というメッセージが込められている
城戸弁護士の妻の浮気相手(遠山淳一?)に関する情報と考察
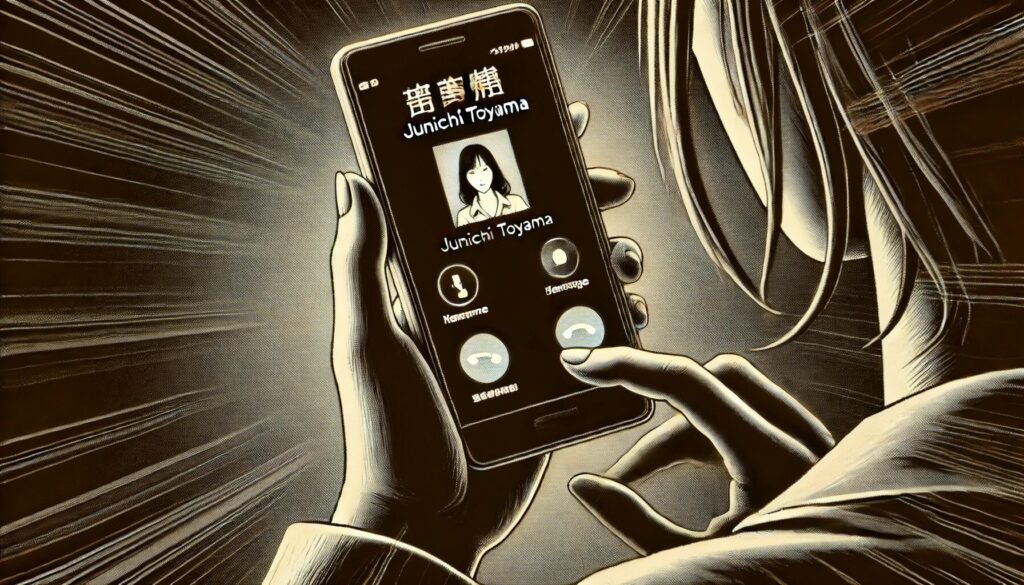
映画『ある男』では、城戸弁護士の妻の浮気が城戸自身の葛藤や心理描写に深く関係しています。ここでは、浮気に関する具体的な情報と「遠山淳一」が浮気相手である可能性について整理し、わかりやすく解説します。
城戸弁護士の妻の浮気が示唆する意味
映画『ある男』では、城戸弁護士の妻の浮気が物語において重要な役割を担っています。城戸はその事実に気づきながら、「気づかないふり」をしています。
この姿勢は、城戸が「帰化した在日3世」としての自らの立場に不安を抱え、「今の家庭を壊したくない」という思いからきていると考えられます。妻の不倫は、彼の「家庭の脆さ」を象徴する重要な要素となっており、その背景には以下の要素が関係しています。
- 妻が不倫相手と二人で飲みに行ったことを疑っている様子が描かれている
- 妻が「次の子供が欲しいから引っ越そう」と提案していたが、その後「やっぱり今はいい」と急に意見を変えた
これらの描写から、城戸は「自分は妻に愛されていないかもしれない」という不安を抱きながらも、家庭の崩壊を恐れて現実に目を背ける選択をしたと考えられます。
「遠山淳一=浮気相手」説について
映画内には「遠山淳一」という名前が登場しますが、彼が浮気相手であると確定した情報はありません。ただし、次の根拠からその可能性が推測できます。
【1】妻の携帯に表示された名前
映画の終盤では、城戸が妻の携帯の着信に目を向けるシーンが描かれています。このとき、「遠山淳一」という名前が表示される場面があったとする意見があります。この描写があった場合、「遠山淳一」が妻の不倫相手である可能性が高いと考えられます。
【2】映画内で「遠山淳一」という名前が登場する意味
映画では浮気相手の名前は直接明かされていませんが、登場人物の一人として「遠山淳一」が挙げられているため、「城戸弁護士の妻の浮気相手が遠山淳一である」という見解が生まれています。
【3】城戸弁護士の葛藤との関連性
城戸弁護士は、在日3世としてのアイデンティティや社会的な立場に葛藤を抱えており、妻の不倫はその心理的不安をより深める要因となっています。
「遠山淳一」が浮気相手であるならば、城戸の葛藤や孤独感を象徴する重要な存在として位置づけられている可能性があります。
原作小説と映画版の違い
原作小説では、城戸弁護士の妻の浮気は軽く触れられる程度で、映画ほどは強調されていません。
一方で、映画版では「家庭の崩壊や不安」がより濃厚に描かれ、そのため浮気の要素がより重要な役割を担っています。
浮気相手としての「遠山淳一」の可能性と未確定情報
現時点で「遠山淳一=浮気相手」という確定情報はありませんが、次の要素からその可能性が浮上しています。
- 妻の携帯に「遠山淳一」という名前が表示されたという説
- 城戸の心の葛藤を深める要素として、登場人物「遠山淳一」の存在が物語に組み込まれている可能性
- 原作と映画の描写の違いから、映画版で浮気の要素がより強調されている点
まとめ
映画『ある男』において、城戸弁護士の妻の浮気は、彼の「アイデンティティの揺らぎ」や「壊れやすい幸せへの執着」を象徴する重要な要素です。
「遠山淳一」が浮気相手であるかどうかは映画内で明確にされていないものの、ストーリーの流れや城戸の葛藤の描写を踏まえると、その可能性が示唆されていると考えられます。
確定情報として「遠山淳一=浮気相手」と断定するのは難しいものの、映画のテーマである「本当の自分と偽りの自分の境界」というメッセージを強く示唆する重要な伏線の一つとして、考察の余地が残されています。
城戸弁護士は戸籍を変えたのか?
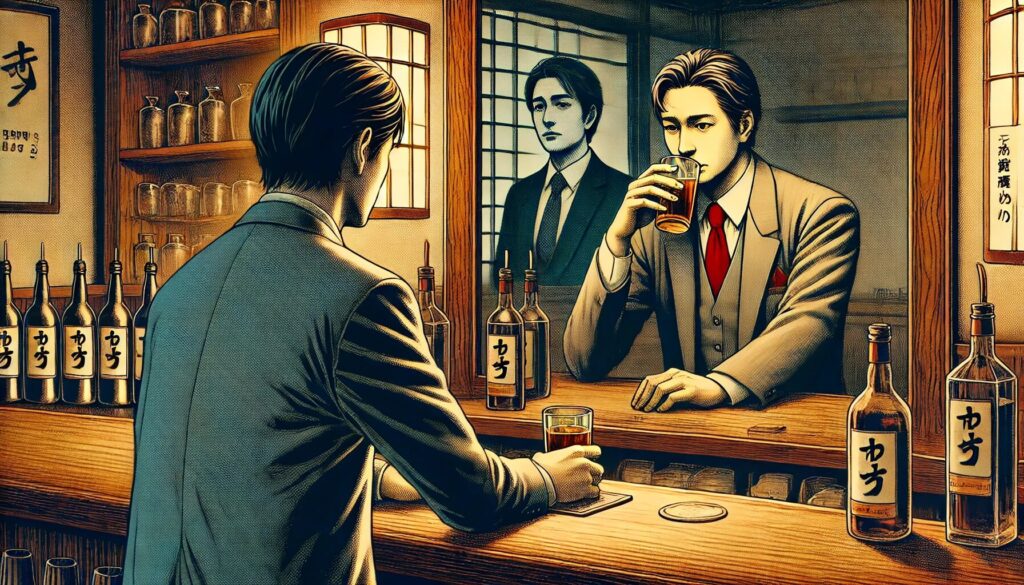
映画『ある男』のラストで描かれた城戸弁護士の行動に対し、「彼は戸籍を変えたのか?」という疑問を持つ視聴者が多くいます。物語の伏線やラストシーンの描写を踏まえると、城戸弁護士は戸籍を変えてはいないと考えられますが、その理由や解釈について詳しく解説します。
城戸弁護士が戸籍を変えたという説
映画のラストでは、バーのシーンで城戸が「私は伊香保温泉の老舗旅館の次男です」と自己紹介しています。この発言が「城戸が戸籍を変え、別人になった」という解釈につながる理由には以下の点があります。
- 城戸の葛藤の深さ:城戸は在日3世という自らのルーツに葛藤し、妻の不倫や家庭の不安定さも重なり、「別の人間として生きたい」という願望を抱えていました。そのため、戸籍交換という行動に走ったのではないかという考えです。
- バーでの自己紹介:この場面は、映画の冒頭でも同じシーンが描かれており、物語全体を象徴する重要なシーンとして位置付けられています。
城戸弁護士が戸籍を変えていないという説(有力説)
一方で、城戸が実際に戸籍を変えていないという解釈の方が妥当であると考えられます。その理由は以下の通りです。
【1】バーでの自己紹介は「遊び心」の可能性
映画の原作では、城戸が「伊香保温泉の旅館の次男です」と名乗るシーンは、物語の中盤に登場しています。このシーンは、単なる「遊び心」や「憂さ晴らし」として描かれており、戸籍交換とは無関係でした。映画版では、このシーンがラストに置き換えられたことで、城戸が「別人として生きる願望」を抱えていることを象徴していると解釈できますが、実際に戸籍を変えたわけではないと考えられます。
【2】戸籍交換に必要な過程が描かれていない
映画では、戸籍を変えるために必要な仲介人とのやり取りや、具体的な戸籍変更の過程は一切描かれていません。戸籍交換がテーマである本作において、その重要なプロセスが描かれていない点からも、城戸が本当に戸籍を変えたとは考えにくいでしょう。
【3】「なりたい自分」と「今の自分」の葛藤
映画では、原誠が「死刑囚の息子」という過去を背負い、その苦しみから戸籍を変えました。これに対し城戸は、「在日3世」である自らのルーツに葛藤しつつも、その事実からは逃げずに今の自分を受け入れようとしています。バーで別人を演じる行動は、「ほんの一瞬、別人として生きる願望を満たすための行為」だったと考えるのが自然です。
まとめ
映画のラストに描かれた城戸の行動は、戸籍を変えたのではなく、「別人としての自分を演じてみたい」という願望の表れであると考えられます。これは、映画のテーマである「アイデンティティの葛藤」を象徴しており、城戸が「本当の自分を守るための一時的な逃避行動」だったと解釈するのが最も自然でしょう。
バーのラストシーンに隠された意味とは?
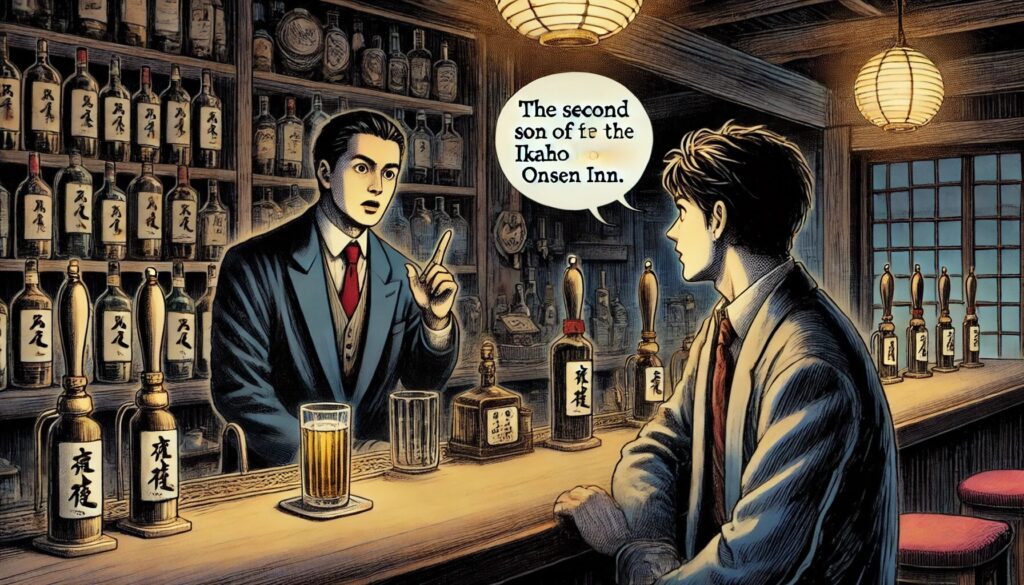
映画『ある男』のラストシーンでは、バーで城戸弁護士が「伊香保温泉の旅館の次男です」と語る場面が描かれています。この印象的なシーンには、物語全体のテーマが凝縮されています。ここでは、バーのラストシーンが持つ深い意味を解説します。
ラストシーンの意味
このシーンは、物語の冒頭とラストに同様のシーンが描かれており、次の3つの重要な意味が込められていると考えられます。
【1】「別人として生きる願望」の象徴
城戸は在日3世としての出自に対する葛藤を抱え、社会の中で「日本人」としての立場に馴染もうと努力してきました。
その中で、妻の不倫や家族との疎外感が重なり、「本当の自分」と「理想の自分」との間で葛藤していました。バーで「伊香保温泉の旅館の次男」を名乗った行動は、「ほんの一瞬だけでも、自分とは違う人間として楽になりたい」という願望の現れと考えられます。
【2】「本当の自分と偽りの自分」の対比
物語の中心には、「名前」や「戸籍」を通じて「自分が何者か」を問うテーマが描かれています。原誠は「父親が死刑囚」という過去から逃れるために戸籍を変え、全くの別人として生きようとしました。
これに対し、城戸は実際には戸籍を変えておらず、「本当の自分」と向き合う道を選びました。
この対比がラストシーンで強調され、「どんなに現実から逃れたくても、結局は本当の自分に戻るしかない」というメッセージが込められています。
【3】「他人の人生」に対する羨望
城戸が名乗った「伊香保温泉の旅館の次男」という人物は、映画内で実際に登場した本物の谷口大祐の経歴です。
城戸がその名前を借りたのは、原誠が谷口大祐として過ごした「穏やかで幸せな家庭生活」への羨望があったからではないかと推測できます。
これは、城戸が「自分が持たないもの」に引き寄せられ、理想の人生を一時的に追体験するための行動だったと考えられます。
まとめ
映画『ある男』のラストシーンは、「自分とは何者か?」というテーマに深く切り込んだ印象的なシーンです。
城戸が名乗った「伊香保温泉の旅館の次男」という自己紹介は、戸籍を変えたわけではなく、「別人として生きてみたい」という一時的な逃避行動であり、現実から逃れたいという人間の切ない心情が映し出されたシーンだったといえるでしょう。
ラストの「13歳の子供」という発言の意味

映画『ある男』のラストシーンで、城戸弁護士が「13歳と4歳の子供がいる」と語る場面が描かれています。このセリフには深い意味が込められており、物語全体のテーマと密接に関係しています。ここでは、その意味を詳しく解説します。
【1】「13歳の子供」は誰を指しているのか?
城戸の「13歳の子供」という発言は、彼自身の子供ではなく、原誠が名乗っていた谷口大祐の家族に関連していると解釈できます。谷口大祐(=原誠)は、里枝との間に4歳の娘・花をもうけており、13歳の子供は里枝が前の夫との間に生まれた子供です。
このため、城戸が語った「13歳と4歳の子供」は、原誠(谷口大祐)の人生を象徴していると考えられます。
【2】なぜ城戸は「13歳の子供がいる」と言ったのか?
このセリフは、城戸が原誠(谷口大祐)の人生を投影した結果であると解釈できます。原誠は「父親が死刑囚」という事実に苦しみ、戸籍を変えて「谷口大祐」としての新たな人生を手に入れました。その結果、彼は4歳と13歳の子供と共に穏やかな家庭生活を築くことができました。
城戸はその人生に共感し、「原誠が得たはずの幸せな家庭生活を自分も体験してみたい」という願望が、あのセリフに込められたのです。
【3】「13歳の子供」というセリフが示す象徴的な意味
映画『ある男』は、「名前」や「過去」から逃れることの難しさを描いています。原誠は父親が殺人犯であるという過去に苦しみ、谷口大祐として新たな人生を歩みましたが、その努力も事故という突然の出来事で途絶えてしまいます。
一方の城戸は、在日3世として日本社会に溶け込むために葛藤し続ける人生を送っています。
そのような状況で、城戸が「13歳と4歳の子供がいる」と語ったのは、原誠が一時的にでも手に入れた「家庭の幸福」に対する憧れがあったと考えられます。
まとめ
「13歳の子供」というセリフは、城戸弁護士が「自分とは別の人生を生きたい」という願望を象徴しています。これは、原誠が過ごした短いながらも幸せな家庭生活に対する羨望や、「自分ではない他人として生きる」という映画のテーマが込められた象徴的な言葉だったと解釈できます。
このように、『ある男』の物語の複雑さや、ストーリー展開の好みは人それぞれです。実際に『つまらない』と感じた人の意見がどのようなものか気になる方は、こちらの記事をご覧ください。→ 映画『ある男』のレビュー検証|つまらないと評価された理由とは?
原作小説と映画の違いを比較
映画『ある男』は、平野啓一郎の同名小説が原作となっていますが、物語の展開や登場人物の描かれ方にはいくつかの違いが存在します。ここでは、ストーリー展開の違いや演出の意図など、原作と映画の相違点を詳しく解説します。
【1】原作では「バーのシーン」は中盤に登場
映画版のラストシーンで描かれた「バーのシーン」は、原作小説では物語の中盤に登場しています。
原作では、城戸が「自分は伊香保温泉の旅館の次男だ」と名乗る場面は、単なる「遊び心」や「憂さ晴らし」として描かれています。
一方、映画版ではこのシーンがラストに配置され、城戸の「別人として生きる願望」や「本当の自分とは何か?」というテーマが強調される構成になっています。
【2】原作では「仲野太賀演じる本物の谷口大祐」の過去が詳しく描かれる
原作では、本物の谷口大祐(仲野太賀)の人物像がより詳細に描かれています。
彼は家族との不仲や過去のトラブルから逃げるために戸籍を変えた経緯が語られ、その動機に深みが加えられています。
一方、映画ではこの部分が簡潔に描かれ、原誠(=谷口大祐)に焦点を当てる構成となっています。
【3】原作の城戸弁護士は「妻の不倫」にあまり動揺しない
原作の城戸弁護士は、映画版よりも妻の不倫に対して冷静な対応を見せます。
原作では、城戸は妻の浮気を知りつつも「それでもこの家庭を守りたい」という冷静な判断を下しています。
一方、映画版では、城戸が不倫の事実に動揺し、「自分の人生をやり直したい」という願望がより色濃く描かれています。これにより、映画版では城戸の葛藤や心の揺れがより強調されています。
【4】映画版は「救い」を意識した結末
原作では、登場人物たちの葛藤や苦悩がよりシリアスに描かれ、全体的に重苦しい雰囲気が漂います。
対して、映画版では「本当の自分に向き合うことで前向きに生きていく」というテーマがより強く打ち出され、観客に「救い」を感じさせる余韻を残しています。
その象徴が、「13歳と4歳の子供がいる」というセリフであり、城戸が「本当の自分」を受け入れつつ、理想の自分への憧れを滲ませる演出となっています。
まとめ
映画『ある男』は、原作のテーマを踏襲しつつ、より「人間の葛藤」や「自己の再生」に焦点を当てた演出が特徴です。
特に、「バーのシーン」をラストに配置することで、城戸弁護士の苦悩や、「本当の自分とは何か?」という物語の根幹を強く印象付けています。
原作と映画の違いを理解することで、作品の持つメッセージがさらに深く心に響くでしょう。
作品が伝えた本当の幸せとは?
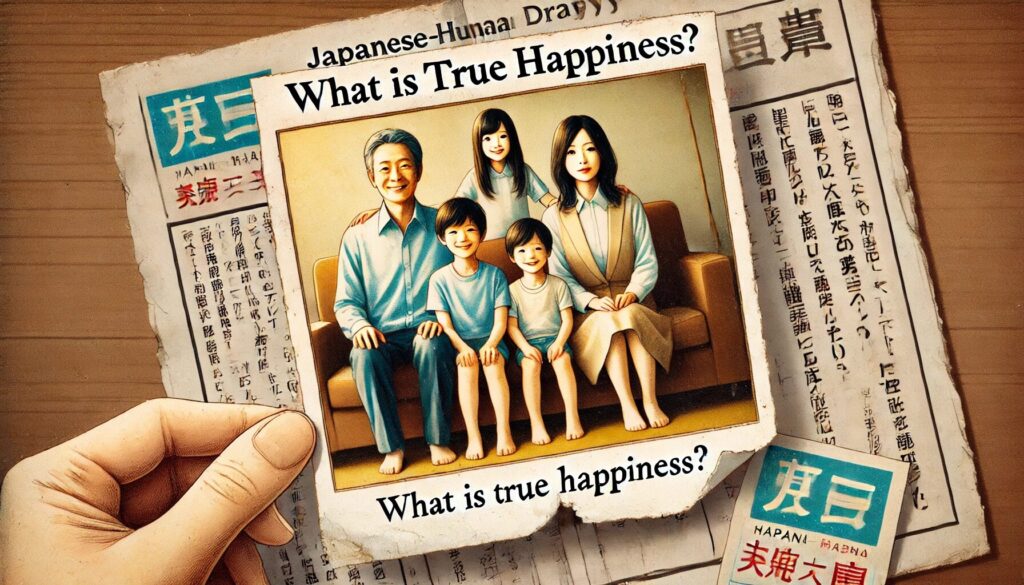
映画『ある男』は、登場人物たちの苦悩や葛藤を通じて、「本当の幸せとは何か」というテーマを深く問いかける作品です。特に、原誠、城戸弁護士、里枝という3人の視点から、幸せの形が異なるにもかかわらず、共通する感情が浮かび上がってきます。ここでは、映画が描いた「本当の幸せ」とは何かを紐解いていきます。
【1】原誠が追い求めた「平凡な日常」の幸せ
原誠は、「死刑囚の息子」という消えない過去に苦しみ、戸籍を変えて「谷口大祐」として新たな人生を歩む決断をしました。彼にとっての幸せは、社会的な成功や富ではなく、「家族と共に平穏に暮らすこと」でした。
過去の影に怯えながらも、里枝と共に家庭を築き、子供と過ごす時間は、原誠にとって最もかけがえのない幸福だったのです。彼が望んだのは、特別ではない「普通の人生」であり、平凡で温かい日常が彼にとっての救いでした。
しかし、原誠はそのわずかな幸福すら突然の事故で失ってしまいます。「幸せとは、どれだけの時間ではなく、どれだけ濃く生きるか」という儚さが描かれたことで、原誠の得た幸福がより重みのあるものとして映し出されました。
【2】城戸弁護士が感じた「自分の居場所」への渇望
城戸弁護士は、在日3世として日本社会に溶け込むために苦悩し続ける人物です。彼は「日本人としての自分」を築こうと努力し、安定した家庭や社会的な成功を手に入れます。しかし、妻の浮気や自身のルーツへの葛藤を抱え、「自分の居場所がどこにもない」という孤独に苛まれます。
その中で、原誠の人生に強く共感し、「自分も別人として生き直したい」と感じるようになります。映画のラストシーンでは、城戸が「13歳と4歳の子供がいる」と語る場面が描かれていますが、これは「原誠が手に入れたはずの家族の幸せ」に対する城戸の憧れや願望が込められた言葉です。
つまり、城戸が求めていた幸せは、社会的な地位や物質的な成功ではなく、「本当の自分を受け入れ、安心して存在できる場所」だったのです。
【3】里枝が選んだ「過去よりも今を生きる」幸せ
里枝は、かつて子供を亡くし、離婚という苦しい経験を乗り越えて原誠と再婚しました。原誠が「谷口大祐」として生きていたことが判明した後も、「名前が何であれ、彼が家族に愛を注いだ存在だった」という事実は変わらない」と受け入れる姿が印象的に描かれています。
これは、「人は過去や出自に関係なく、目の前の人を信じ、今を生きることで幸せを感じられる」というメッセージとも解釈できます。
特に、息子が原誠について「親にしてほしかったことをしてくれた」と話す場面は、里枝が「過去の罪」ではなく、「共に過ごした時間の温かさ」を大切にしていたことを象徴しています。
【4】「幸せ」に対する映画のメッセージ
映画『ある男』が伝えたのは、「本当の幸せとは、肩書きや過去の重さにとらわれず、今この瞬間に感じる愛や温かさである」という普遍的なメッセージです。
登場人物たちは、誰もが過去の傷やレッテルに苦しみながらも、「自分を受け入れてくれる場所」や「かけがえのない人との時間」に幸せを見出しています。
【5】「本当の幸せ」の要素まとめ
- 原誠にとっての幸せ:「平凡な日常の温かさ」
- 城戸弁護士にとっての幸せ:「自分の存在が受け入れられる場所」
- 里枝にとっての幸せ:「過去にとらわれず、今を大切に生きること」
まとめ
映画『ある男』は、「自分の過去やアイデンティティとどう向き合うか?」という深いテーマを通じて、「本当の幸せとは何か」を問いかける作品です。
「幸せは肩書きや出自ではなく、今をどう生き、どれだけ愛を注ぐか」という温かくも切ないメッセージが、観る人の心に深く響く物語となっています。
映画『ある男』のネタバレ考察と解説を総括
- 映画『ある男』は2022年公開の日本映画
- 監督は石川慶、主演は妻夫木聡、安藤サクラ、窪田正孝
- 原作は平野啓一郎の同名小説
- ジャンルはサスペンス・ヒューマンドラマ
- 主人公の城戸弁護士は在日3世という葛藤を抱える
- 原誠は「死刑囚の息子」という出自から戸籍を変えた
- 本物の谷口大祐は家庭の不和から戸籍を捨てた
- 里枝は夫が別人だった事実に直面しながらも愛を貫いた
- 城戸弁護士の妻の浮気が家庭崩壊の不安を強めた
- 「遠山淳一」は浮気相手の可能性があるが確定ではない
- ラストシーンのバーで城戸が別人を演じる場面が象徴的
- 「13歳の子供」の発言は原誠の家族への憧れを示唆
- 原作と映画では、城戸の葛藤や浮気問題の描写に差異がある
- 映画版は「本当の自分とは何か?」というテーマが強調されている
- 幸せとは「今この瞬間の愛や温かさ」を大切にすることと描かれた